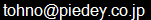|
||||||
|
君は知っているか。 美しく可愛く献身的な少女達からなるメイド達。 そして彼女らのご主人様となるオターク族。 その2種類の住人しか存在しない夢の中の世界を。 ある者は、桃源郷と呼び。 またある者は、狡猾なる悪魔の誘惑に満ちた監獄と呼ぶ。 それは、どこにも存在しないナルランド。 住人達がボックスマン・スーフィーアと呼ぶ世界。 そして、悪魔と取引したたった一人の男によって生み出された世界。 前回のあらすじ §新人メイドの悲鳴を楽しむ悪趣味なボックスマン達。しかし、悪趣味ではない気品のあるボックスマンが二人いた。彼らのうちのどちらかをご主人様と仰ぎたいメイ。だが、ライバルは多い。しかも、メイのメイド服はあまりにもデザインが時代遅れだ……。はたして、どのボックスマンがメイをメイドとして指名するのだろうか!! 第6話『ご主人様達からの熱い視線、そして新人メイド達の冷たい視線』 §メイは、恐怖で体が微かに震えるのを止められなかった。 こんな時代遅れのメイド服を着た場違いな自分がご主人様に指名されることはなく、間違いなく売れ残る。 売れ残れば、メイドにはなれない。 このボックスマン・スーフィーア世界には、ご主人様とメイド以外の存在が生きる余地はない。もちろん、まだメイドになっていない者達や、メイドを引退した者達が居ないわけではない。しかし、彼女らは人生のいずれかの時点でメイドであるからこそ、この世界での存在価値を与えられるのだ。もし、人生で一度もメイドにならないような事態があるとすれば、それはこの世界で生きることを許されないことになる。実際、メイドになることを拒絶し、脱走を試みた者達は数年ごとに出ているが、彼女らは常に厳しい刑罰に処せられ、そして最終的にボックスマン・スーフィーア世界から追放処分されている。誰でも良いから、ボックスマンに指名してもらわねばならない。 いや、それでも恐怖が消えることはない。メイド達の悲鳴を楽しむという、あの残酷なボックスマンの誰かに指名されたらどうするのか。毎日、恐怖に悲鳴を上げることでご主人様の萌えになる、などという日々を正気のまま過ごせるだろうか。 すっと優しい手がメイ頬に触れた。 「怖がることはないよ、新人メイドちゃん」という声が聞こえた。 それは、白いスーツのボックスマンだった。 「そうそう」と彼の横に立ったワイン色のスーツのボックスマンがうなずいた。 二人のボックスは、まっすぐにメイに向けられていた。ボックスの穴から小さく見える目は、メイの顔をまっすぐに見ているように思えた。 メイは戸惑った。 これはどういうことだろうか。 他のメイドではなく、二人はメイを見ている。 こんな時代遅れのメイド服を着た自分をなぜ……。 「安心しなさい。彼らもけして悪い人間じゃない」と白いスーツのご主人様は他のボックスマン達の方を見やった。 「そうだ。悲鳴を聞きたいというのは悪い趣味だと思うが、だからといって毎日メイドの悲鳴を聞きたいと思っているわけではないよ」ワイン色のスーツのご主人様が言った。「もし、彼らの誰かが君のご主人様になったとしても、きっと優しく扱ってくれるはずだ。真にメイドを傷つける残酷なご主人様など、そうそういるものではないよ」 「だから、もう体を震わせて怖がることはない」と白いスーツのご主人様は言った。顔が見えないのに、まるで微笑まれたような気がして、メイは顔を赤らめた。 そしてハッと気付いた。 どうしてこの二人がメイに声を掛けたのか。その理由は、メイの体が震えていたからなのだ。メイド服の種類ばかり気にしていたが、他にも理由があったということだ。 それに気付くことは、別の悲惨な現実をむき出しにした。 つまり、震えているメイドであればこそ、二人は声を掛けてきたのだ。震えが止まってしまった今、もはやメイには二人から声を掛けて貰える理由が存在しない。 「でもね」とワイン色のスーツのご主人様が言った。「君のことは、他の誰でもない。僕が落札するつもりだから、何も不安を感じることはないよ」 メイは、その言葉にショックを受けた。まさか、メイド達がみな羨望のまなざしを送るワイン色の王子様が、メイを選ぶとはっきり言い切るとは。 さっと周囲の空気が変わるのをメイは感じた。他のメイド達の嫉妬の視線が突き刺さるようで痛い。 メイが、どうすれば良いのかを考えようとしてかえって混乱を深めたとき、白いスーツのご主人様が声を上げた。 「おいおい。ずいぶんと大胆なもの言いだな。自分一人で勝手に落札相手を決めてしまうつもりかい? 僕もいるのに、そう簡単に落とせるとは思わないでくれよ」 更に、他のボックスマン達がざわざわと声を上げ始めた。 「白きプリンスまで名乗りを上げたぞ」 「レッド・ダンディだけでも強敵なのに」 「俺達は、無理なのか」 「でも欲しいぞ、あのメイドは萌えだ」 「オレも萌えだ」 「欲しい」 「欲しい」 「とても欲しい」 「でも、無理だ」 「無理だ」 「無理だ」 メイは、戸惑った。 あの二人だけではない。他のボックスマン達も、メイを欲しがっている。全てのボックスマンではないが、かなり多くのボックスマンがメイを求めている。 だが、メイはどう対応して良いのか分からなかった。リハーサルでは、このような事態は起きなかったのだ。 そんなメイを、入り口に立っていた年配のメイドが救った。 彼女はよく通る声で叫んだ。 「ご主人様方。新人メイド達のご挨拶とお披露目の時間はこの後にたっぷりと取っております。どのメイドを指名されるかは、全ての新人メイド達の挨拶をご覧になった後でも遅くございません。まずは、会場でおくつろぎ下さいませ」 ボックスマン達はその声に促され、部屋の奥の方に移動していった。 メイはピンチが去り、ホッとため息をついた。 だが、ホッとするのは早かった。 ボックスマン達が去ると、メイは新人メイド達に囲まれた。 「どういうことなの。どうして、あんただけがあれほど……」 新人メイドの一人が、声量は抑えつつも激しい口調でメイに詰め寄った。 激しい女の嫉妬を叩き付けられて、メイはたじろいだ。 続く.... §なぜメイだけがボックスマン達の注目を集めるのだろうか。メイにはその理由が分からない。彼女がメイドのプリンセスだと言う秘密が知られているのだろうか。いやそうではない。 そして、分からない理由で新人メイド達の嫉妬心を叩き付けられるメイの未来はどちらだ!? (遠野秋彦・作 ©2005 TOHNO, Akihiko) |
|
||
|
|