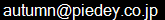10月30日放映のROD。
これは、またまた凄いものですね。
凄いというのは、中身の凄さもさることながら、取り上げている舞台と状況がマニアックです。普通の人に、これは分からないのではないか、と思うぐらいのマニアックさですね。いや、それが何を意味しているのか分かっても、その気持ちと面白さが分からないかもしれません。
本ですよ、本。本をひたすら買いあさる長女。
そして、ビル1つが彼女の本棚のようなもの、という今はもう居ない人物。このビル1つが本棚、というのはけして誇張ではありませんね。本当に本を読み続ければ、この程度のスペースは間違いなく必要です。アニメ的誇張ではないと思います。であるからこそ、たいへんに魅力のあるアニメだと思います。
内容を見ると。
まず、旗坊扱いされるアニタ。
洗面所にも本。どこにでも本が入り込むという状況が面白いでうすね。
マスコミが謎の動物として取り上げる紙技。
テレビを消すと、画面に反射する室内の人。しかも動いて演技するところが凝っていますね。
4人で過ごす、どこかだれた感じ。
大きなベッドにジャンプすると埃。いちいち掃除して洗濯しなければならない手順が、いちいち藁とシーツで作らねばならないアルプスの少女ハイジの寝床のような感じですね。名作アニメに近い感覚があります。
立派な掃除機。
鳩と見つめ合う次女。この妙なおかしさ。
3人で いろいろ寝てみる ベッドの上
これも可笑しいですね。
狭くて暗いところが好きな次女。変なところを自分の部屋にしたがりますね。
インタビュアーに絡まれるねねね先生、というテレビ映像を見ながら「私たち、ボディガード……」とぼそっと言う次女。そうそう。本当は居候ではなくボディガードだったわけですね。
先生を守ろうと地図で神田を捜すと神保町を発見。これが、とんでもない大事件に感じられる長女と次女。
いざ神保町に行くと自由行動になる3人。
舞い上がる長女。
ねねね先生は、作品の文庫化に際して書き直すところがあれば、と編集者に言われますが、「未熟だから読み返したくない……」と。
川俣さんに聞くと「古い原稿は驚くほど下手くそで、見ると焦りまくるから見たくないよ。よく、こんな下手な文章を書いていたと思うよ」と言いました。
遠野さんに聞くと「うーん分かる。それがゆえに、ラト姫物語の第2版が未だにリリースされていなって面がかなりあったりするし」
ファンレターを読む勇気がない、ねねね先生。
後輩少女作家。ひらひらのファッションに紙袋一杯のファンレター。このギャップが凄いですね。しかも、ねねね先生と同い年。
「この店の本、全部下さい」と言う、いってしまった顔の長女。壮絶ですね。こういう台詞を言ってみたいものです。
外から見えるエレベータ。これは書泉グランデがモデルでしょうか。書泉グランデは地下にも売り場があったと思いますが、エレベータで行けたかどうか記憶にないですね。記憶にないというか、そもそもあまり神保町、あるいは書泉グランデは行かないようにしているので。行ったら、欲しい本が何冊も発見されてしまって、とてもお財布への打撃が致命傷になると分かっていますから。だから、あそこは行ってはならない場所です。
地下の謎の本屋と謎の少年。こんなファンタジーのような場所は、実際の神保町には無いでしょうね。でも、こういう場所があると空想することは、素敵なファンタジーです。
本を買いすぎて、歩きながらひっくり返る長女。重くて、ふらふらしても、全くつらそうではありませんね。人生の至福のひととき。
居なくなった大切な人の居所。こういう、そこに存在しない人の話で感情を盛り上げるところも、見事な演出ですね。
勘違いで始まる青空古書市。
実は、長女の仕業と分かって、げしげしと言いながら長女を蹴るねねね先生。本当に口で「げしげし」と言うのは、マシンロボレスキューのハザード大佐の「シュタッ」にも似たセンスある演出ですね。
そして、最後にはテラスのテーブルまで本。最後までこれですからね。素敵な三姉妹です。
今回の一言 §
この三姉妹のように生きてみたい…… (けっこう本音)
ただし、ダメな行動の数々の尻ぬぐいをしてくれる、ねねね先生がいる場合に限る。