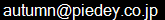|
||||||
|
ふしぎの海のナディアのN-ノーチラス発進シーンは、宇宙戦艦ヤマトの発進シーン(第2話)のオマージュとも言うべきもので、ほとんどの台詞やシーケンスがヤマトをなぞる形で進行します。 そこで、ナディアの音声にヤマトの映像を合わせるという発想が出てきます。 それが上手く噛み合うのはある意味で当然と思えるかもしれません。 しかし、当然と思うのは間違いです。 その理由は後で解説します。まずはごらんになって下さい。 MAD Yamato&NADHYA §(画像公開ポリシー) 見所 §意図的にヤマトそっくりにナディアが作られているとしても、実はそのままではヤマトの映像に差し替えることができません。それは多少の編集が必要……というレベルの話ではありません。 たとえば動きのスピードを変えるといった方法でタイミングを合わせているような話を別にすれば、大きなポイントは3つあります。 第1のポイント・敵はシュルツとガンツではない §ヤマト序盤の敵は、冥王星前線基地の司令官シュルツと副官ガンツです。しかし、第2話の時点でヤマト(を建造している地下工場都市)を偵察に来たガミラス宇宙空母を直接指揮しているのは、遠くガミラス本星にいるデスラー(肌色デスラー)本人です。 ヤマト第2話で宇宙空母が撃破されるシーンでは……、 「きゅ、九州坊ヶ崎地下の地下都市は単なる工場ではなく、そ、それは戦艦の工場でした!」 「ふっふっふ。たたきのめせ」 「総統、残念ながら手遅れです。本艦は、本艦はもう!(ちゅどーん)」 などというような台詞(記憶違いがあるので正確ではない……、って記憶だけでここまで書けるのかよ!)で沈むわけです。 必然的に第2話には敵の幹部の会話映像はありません。 そこで、このMAD映像では、別のエピソードからシュルツとガンツの映像を持ってきて組み込んでいるわけです。 実に凝っていますね。 第2のポイント・ヤマトにバリアはない §ナディア側には、発進直前に攻撃されバリアで防ぐ描写があります。 しかし、ヤマトの第2話には、それに類する描写はありません。それどころか、ヤマトにはバリアに類する装備そのものが存在しません。ゆえに、ここだけは、完全にナディアのオリジナルのシーンです。 従って、音声に含まれるバリア云々のシーンに対応する映像は、ヤマトのこのエピソードに無いどころか、どのエピソードを見ても存在しません。 そこで、このMAD映像では、素材を上手く加工して、それらしい映像を作り出しています。ここも、この映像の大きな見所の1つですね。 第3のポイント・このフネにはまだ作業員しかいないのだ §第2話の時点で、ヤマトに乗り組んでいる正規乗組員はおそらく沖田、古代、島、佐渡、雪だけです。残りは工場の作業員です。ゆえに、第1艦橋に相原らの他のクルーがいるシーンは、第2話には存在しません。そのあたりは、別のエピソードから持ってきて組み入れているようです。 ちなみに、スクリーン上の爆発を見ているシーンは、おそらく第3話のものです。 ヤマトの思い出 §宇宙戦艦ヤマト本放送は、アルプスのハイジ少女の裏番組です。(そして、その更に裏が「猿の軍団」) そして、家族がハイジを見るために、家の中にたった1台しかないカラーTV(当時としては普通のこと)でヤマトを見ることが許されず、モノクロTVで泣く泣く見るしかなかった……というトラウマがあります。何せ、色が付かないモノクロTVで見ていると、「赤い地球」が理解できないのです。 さて、ナディアの庵野監督も、本などの記述からすると、全く同じ体験をしていたようです。 そういう意味で、庵野監督のヤマトへの思い入れはとても他人事に思えません。 私の場合、暗記しているヤマトの台詞は上記の3行程度ではありません。特に第2話のヤマト発進シーケンスは、今でもかなり「資料を見ずにそらで」言えます。「各砲連動仰角9時から9時5分へ自動追尾。セット20,45。スイッチ艦長に渡します」とか「主動力線コンタクト、メーンエネルギースイッチオン、傾斜復元船体起こせ!(船体起こせ!) 補助エンジン両舷全速取り舵一杯!」とか、もっと有益な知識を覚えれば良かったと後悔するような役に立たない知識の数々が出てきます (笑。(しかし、これらの台詞が正しいという保証は何もない) たぶん、庵野監督の事情もさほど違わないのでしょう。資料をほとんど見ないで、あのシーンをナディアで再現するぐらい、朝飯前だったのでしょう。 そういう意味で、私にとっての庵野監督とは、心情的に嫌いになれない人なのです。 |