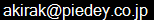この本は、出版当時にすぐに買ったものです。奥付を見ると平成13年となっているので、3年前のことになりますね。これは入院前のことですから、かなり前のことに感じられます。買った理由は難しいことは何もなく、巷説百物語はとても面白いものだったので、続編も喜んで買ったというわけです。
そして、最初の1編を読んで面白かった記憶があります。面白すぎて読んでしまうのはもったいなさ過ぎる。そんな感じで、残りを読まないまま放置されていました。
続編の続編 §
しかし、更にその続編となる後巷説百物語を買ったことにより、これを読み切っても問題無い状況になりました。しかし、そのころには、とっくにこの本のことは忘れていたのも確かです。大切なものを、後生大事にしまい込んでいると、かえってそのことを忘れてしまうことがあるものです。
転機は直木賞 §
そこで1つの転機となったのは、後巷説百物語が直木賞を受賞したことです。既に持っている本が、こういう章を受賞することは初めての経験なので読んでみたいと思いました。しかし、その前に、まだ読み終えていない続巷説百物語を読み切る必要があるだろう。そう思って、ちょっと前の本の山から掘り出して読み始めました。
やはり面白い §
読んでみると、やはり面白いですね。
既にある物語と絡む話もあり。
百介の視点から見た状況の描き方も面白いし。
相変わらずの痛快さもあるし。
そして、又市達の行ったことの数年後を描くという実に面白い作品もありますね。その場を綺麗に納めるだけで終わるのではなく、その後の状況も描いているのが面白いと思います。
特に良かったのは、殺戮魔の殿様がおかしくなった原因として、金山の存在があるというあたりですね。人をおかしくしてしまう魔力があるのでしょう。妖怪や怨霊よりも、金の方が恐ろしい怪物なのかもしれません。
昔よりも、より分かるようになった §
もう1つ、この本を買った時点から現在までの間に、歴史資料館巡りなどということを始めたために、書かれていることが一層良く分かるようになった、ということもあります。この当時の建物、ファッション、社会システム、風俗などが、より具体的なビジュアルとして頭に思い描けるようになりました。これは、大きな収穫かもしれません。今読んで良かったと言えるかもしれません。