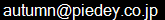アニメにおける3次元コンピュータグラフィック(3DCG)の利用については、前々から何か書こうかと思っていました。ですが、丁度、あまりに「なんじゃこりゃ~」という3DCGパートを含むアニメを見てしまい、書き始めることを決めました。
そうです。実際に、アニメの中で3DCGが上手く使われているかというと、そうではない作品の方が多いと思います。
たとえば、3DCGを上手く使えていない一例として、トランスフォーマー・カーロボットの変形シーンを上げておきましょう。手書きの他の同シリーズの変形シーンと比較して、あまりにも迫力が無く、退屈であると言えます。本当に玩具をカチャカチャ動かして形を変えているようにしか見えません。それに対して、上手く使えている事例として、マシンロボレスキューがあります。こちらは、画面の中をビュンビュンとメカが飛び回って合体して、手書きの合体シーンと比較して、遜色はありません。この2つの変形シーンを見比べれば、使い方一つで、圧倒的な見応えの差を生じていることが分かるでしょう。
では具体的にいったい何が違うのか、それをこの企画では書いてみたいと思っています。歴史から述べて、具体例をあげて、それを分析し、何かの結論を得たいと思います。
ただし、と~のはこの世界の素人に過ぎませんから、内容は完全ではありません。多くの間違いを含むかも知れません。その点は、ご了承下さい。
現時点での大まかな予定を以下に示します。これは予定なので、実際にどうなるかは保証できません。
- 歴史を振り返る~ゴルゴとレンズマン
- 動く愉しさとDoGAの功績
- ハリウッド映画に見るリアルか非リアルかの問題
- トゥーンシェーダーの功罪
- かえって画面をチャチに見せる3DCG利用
- カメラワークの不在
- ライティングについて
- 常に汚れているメカ
- なぜキャラクターを3DCGでやらないのか
- まとめ・2Dアニメは3DCGと共存するか?
ご注意: このコンテンツは、「バーチャルネットライター と~のZERO歳」と呼ばれるサイトに書き込まれた内容を変換して、本サイトに転送したものです。このコンテンツの内容は、「と~のZERO歳」という仮想人格が書いたものという設定であり、謎のアニメ感想家トーノ・ゼロと限りなく近いものの、必ずしも同一人格ではないことをお断りしておきます。