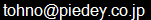|
||||||
|
君は知っているか。 美しく可愛く献身的な少女達からなるメイド達。 そして彼女らのご主人様となるオターク族。 その2種類の住人しか存在しない夢の中の世界を。 ある者は、桃源郷と呼び。 またある者は、狡猾なる悪魔の誘惑に満ちた監獄と呼ぶ。 それは、どこにも存在しないナルランド。 住人達がボックスマン・スーフィーアと呼ぶ世界。 そして、悪魔と取引したたった一人の男によって生み出された世界。 前回のあらすじ §メイドになるために努力し続けた少女達。彼女たちに投げかけられた「ご主人様の萌えになれ」という言葉は、混乱を招いた。自分たちはメイドになるのではないのかと。 だが、それは誤解だった。少女達はメイドになることでご主人様に選んで頂く立場に立つ権利を手に入れる。だからメイドにならねばならない。しかし、メイドになれば終わりではない。ご主人様の望む通りのメイドに更に変わっていくということが、「萌えになる」という意味だったのだ。 時間になり、少女達はご主人様を迎え入れる部屋に並んだ。 ドアが開き、そこから入ってきたご主人様達は、箱を頭に被っていた……。まるで運の悪いメイドを生け贄として捧げられる怪物のように……。少女達は悲鳴を上げた。 第5話『悲鳴を上げる新人メイド達と悪趣味なご主人様達』 §少女達の悲鳴が部屋を満たした。 そのことを、メイはほとんど意識していなかった。メイ自身も、か細い悲鳴を上げていたが、耳は何も聞いていなかった。目は、目の前の箱を被った男達の方を向いていたが何も見てはいなかった。 まるでその場のパニックに飲み込まれて自分というものが消えて無くなったような状況だった。 自分を無くすことと時間を無くすことは同じであった。 悲鳴が部屋を満たしていた時間は、ほんの僅かであったが、それは当事者には無限にも等しい長い時間に感じられた。 「怯える少女の悲鳴、萌え~」 「初々しい声が、萌え~」 「この一瞬が楽しみだ、萌え~」 「最高最高。人生の快楽、萌え~」 メイは、遠くで響く低い声があることに気付いた。 いくつもの箱達が、メイ達を見ている。 箱に開けられた小さな穴が、メイ達を向いている。 その中に、小さく輝くものが見える。 彼らは見ている。 新人メイド達を見ている。 そして、口々に喜びの声をあげている。 彼らは「萌え」と言っている。萌えとはご主人様の言葉だと教えられた。ならば、彼らがご主人様なのだろうか。だが、箱を被っているのは、運の悪いメイドが生け贄に差し出される怪物のはずだ。ご主人様が箱を被っているという話など聞いたことがない。 それに彼らの言い分はどうだ。 メイはようやく彼らの言っている言葉が理解できるまでに冷静さが戻ってきていた。 彼らは怯える少女の悲鳴を楽しんでいる。 それが、彼らの「萌え」だと言っている。 ご主人様の「萌え」になることがメイドの目的であれば、恐怖に悲鳴を上げたメイ達はご主人様の「萌え」になれたのかもしれない。 だが、到底喜ぶ気にはなれなかった。本当に怖かったからだ。 こんなにもメイドを怖がらせる者達が、全てのメイドが待ち望むご主人様であるわけがない。 そうだ、彼らはやはりご主人様ではなく、怪物なのだ。 メイがそう思った時、箱を被った男の一人が喜びのカケラもない冷めた口調で言った。 「下らん。まだ、こんな下らない愚劣な行為を楽しむオターク族がいたのか」 品の良い白いスーツを着た男だった。彼は、明らかに他の男達よりもあか抜けた感じがした。 「同感だね」とワイン色のスーツを着た、ややオシャレな、しかしやはり箱を被った男が答えた。「箱を被った怪物の都市伝説を流して、しかもオターク族とはボックスマンであるという情報を新人メイドには絶対に教えないように強制する。初めてのご対面で綺麗な悲鳴を聞けて大満足ってか? まったく趣味が悪くて泣けてきちゃうね。それでも、趣味が悪い方が多数派だから制度が改まらないってか?」 悲鳴を喜んでいた箱を被った男達……、どうやらボックスマンというらしい、は黙り込んだ。 メイは、この言葉でやっと謎が解けたことを感じた。そうか、ご主人様とはボックスマンと呼ばれる箱を被った男達なのだ。そして、その事実は、「萌え」という言葉と同じように、修行中のメイドには教えてはならないと定められていたのだ。 もちろん、ご主人様が箱を被って顔も見えない不気味な存在だというのは、予想もしない哀しさを感じさせた。 だが、メイは、そのことを夢見た人生の終わりとは思わなかった。 この二人、白いスーツのボックスマンと、ワイン色のスーツのボックスマンからは、まさにお仕えするに値する気品が伝わってきた。 このどちらかにお仕えしたい……、とメイは思った。だが、決定権はご主人様にあるのだ。自分を選んでもらうために、精一杯のアピールをすることはできるが、決めるのはご主人様だ。 そして、メイはふと気付いた。他のメイド達も熱い視線をこの二人に注いでいる。 彼女らに負けるわけにはいかない。 どうか、二人のどちらかが自分を選んで下さるように、とメイはメイドの女神に祈った。 そして、祈るために視線を落とした時、自分の着ているメイド服が目に入った。 そしてメイは蒼白になった。 メイが着ているのは、メイン・ティーのメイド服だ。2世代も古い、あまりに時代錯誤なデザインのメイド服ではないか。こんなメイド服で、誰もが熱い視線を注ぐ最高のご主人様に選んでもらうことなど、できようはずもない……。 メイは目の前が暗くなった。 続く.... §新人メイドの悲鳴を楽しむ悪趣味なボックスマン達。しかし、悪趣味ではない気品のあるボックスマンが二人いた。彼らのうちのどちらかをご主人様と仰ぎたいメイ。だが、ライバルは多い。しかも、メイのメイド服はあまりにもデザインが時代遅れだ……。はたして、どのボックスマンがメイをメイドとして指名するのだろうか!! 第6話『ご主人様達からの熱い視線、そして新人メイド達の冷たい視線』に続く (遠野秋彦・作 ©2005 TOHNO, Akihiko) |
|
||
|
|