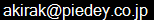「なんだよ大予言って」
「昔ノストラダムスの大予言って流行ったので」
「壮大なホラ話だろ。1999年に世界は滅んでないし」
「まあ、そこは気にするな」
思い出話 §
「じゃあ、予言ってなんだよ」
「その前に昔話をしよう」
「なんだよそれ」
「話は順番だ」
「分かった、何を言いたいんだ?」
「月刊ASCIIの初代編集長の吉崎武さんとは1回会ったことがある。子供の頃に夏休みにバイトしようと思って押しかけたのだが、募集していないとあっさり断られた。その時、実は表現は忘れたが『古いメインフレーマーのような話し方をする』と心配された」
「なんだよそれは」
「今になって、これが解釈できた」
「どういう意味?」
「1980年前後の時代、マイコンなんてオモチャだと言うようなタイプのメインフレーマーがなぜそのようなことを言ったのかという理由。そして、なぜ自分がそういうタイプに似ていたのかという理由。そして、今の自分もそれに似た立場になったということ」
「は?」
「あの当時のマイコンは、無限の可能性ともてはやされていたが、メインフレームが解決すべき問題にはほとんど無力だった」
「ワープロや表計算は無力ってこと?」
「そうじゃない。1980年前後では、まだそれらはマイコンで使用される標準レパートリーに入っていなかった」
「えー」
「アメリカではまだしもWordStarとかあったが、日本ではそもそも漢字をパソコンで打てなかった。世界初のマイコンの表計算はアメリカのVisiCalcだが、これが1979年。もちろん、日本にはすぐ浸透しないし、そもそも日本語が使えない」
「ひぇ~」
「もっとも、メインフレームでもカタカナが使えるだけで日本語ができると主張する例がまだまだあった時代だがな。それでも、やらせたい仕事はいろいろあったわけだ。しかし、当時のマイコンの能力はそれにまるで追いついていない」
「まさか」
「HDDはおろかフロッピーすらついていないマシンで何ができると思う」
「ぎゃふん」
「この構図は結局、今のスマホと同じだよ」
「えっ?」
「いくらマスコミがスマホを持ち上げて、もうパソコンは要らないと言っても、こっちから見れば『あれもできない、これもできない。ユーザー要求の多くが達成できない』と冷ややかに見ることしかできない」
「無限の可能性を持ったマイコンでも、実現出来ないことだらけという過去と同じってことだね」
「そうだ」
もう1つ §
「もう1つ思い出話をしよう」
「なんだい?」
「某パソコンショップで、こっちも客だが別の客にいろいろ説明してしまったことがある」
「そうか」
「その時、こっちのパソコンの方がいいですよ、と説明した。しかし、あとから店員に怒られた。彼らは明らかに将来性の無い劣ったパソコン『も』売りたかったのだ」
「なぜ将来性が無いって言い切れるの?」
「技術的な理由は山ほどあるが詳細は割愛しよう。将来性が劣ると思ったパソコンは確かにシリーズが先細りになっていった。将来性があると思ったパソコンは大帝国を築いた。その未来だけでも十分に適切な推論であった」
「分かったよ。それで、それがどうしたの?」
「今と同じってことだ」
「は?」
「ケータイのショップに行くと、店員は明らかに将来性の無い劣ったスマホを売りたがる。大昔、なぜそんなものを売りたがるのか理解できなかったが、今も同じような光景を目にしているわけだ」
「相変わらず理解できないの?」
「正しい解釈は分からないが、今ならそのように行動する理由はいくつも思いつくよ」
「そうか。そこは大人になった、ということだね」
「そうだな。いろいろな立場に立って多角的に見られるようになった。しかし、同じような光景を繰り返し見ているという意味では、歴史は繰り返している」
「ははは」
根本的な質問 §
「そもそも、1980年前後って君は中学生だよね。なんで中学生が、古狸のメインフレーマーみたいに振る舞えるんだよ」
「いい質問だ」
「説明があるんだよね?」
「もちろんだ。マイコン黎明期には、文化の混濁があった」
「混濁?」
「つまりさ。メインフレーム文化の一部がマイコンレベルに降りてきていた。大型機のあれっぽいのをマイコンでやってみました、というノリの話題もあった。しかし、そのうちにマイコンはマイコンだけで独立した世界になっていった。タコツボに入ったと言ってもいい。そこでは、マイコンしか知らない子供達が満ちあふれた。もちろん、子供と言っても、そこそこの年齢の人も多いけどね」
「そうか。そこで、上の世界を意識した君と、後から来た子供達では話が合わないわけだね」
「それだけじゃない。大阪万博のIBM館で鉄腕アトムをメインフレーム使って読んだ(詳細は不明だが)とか、そんな経験もあるしな。あれに比べればマイコンがオモチャであることも分かる。ライトペンでページを送るのだ」
「当時の水準なら画期的だね」
「他に、ジャンク屋通いというのも理由としてあるね」
「なんだよそれは」
「ジャンク屋にはジャンクパーツが並ぶが、たいていは世代が古いんだ。コアメモリが並んでるのを見たことだってあるんだぜ」
「コアメモリって、どんだけ古いんだよ」
「だからさ。上の世界の存在はそいう形でも見えていたわけ。綺麗なショップにいってマイコンを買い込んで上品に使ってるだけの連中にはけして見えない世界だな」
「そうか」
「リースバックのメインフレームとかミニコンの中古を売っていた店が確か柴崎だかそのへんにあってね。行ったことは無いが、雑誌でよく広告を見た。だから、マイコンという世界で閉じるはずはない、という漠然とした前提はあったよ」
「閉じない君はどこに向かったんだい?」
「だからさ。普通のマイコンマニアと違って、その後はインターフェースとがbitのような雑誌を見るようになったわけだ。そこで、VAX-11で使うUnixは凄くいいとか、そんな記事を日常的に見ていたわけだ」
「ひぇ~」
ならばどうなる? §
「それでその話がどう大予言になるのさ」
「うん。そこがポイントだ」
「どうポイントなの?」
「マイコン時代、業界で主導権を取ったメジャーなプレイヤー達。彼らのうちで残存しているブランドなど、非常に少ない。ほとんどは消えて無くなったね」
「まさか」
「マイコン時代の御三家は、Apple、Commodore、Tandyだけどさ。今でも名前が出てくるのはAppleだけさ」
「まさか」
「業界の主流だったOSはCP/Mだが、今はもう誰も名前すら知らないぞ。開発したデジタルリサーチの名前も一緒にな」
「忘れられた名前だね」
「マイクロソフトなんて、BASIC言語や一部のソフトを作っていただけで、汎用OSは作ってなかったし、ハード製品もやってなかった。確かにBASIC言語は重要な意味があったが、それは重要なパーツ供給源でしかなく、主役ではなかった」
「でも、その後はぜんぜん違うじゃないか」
「そうだ。だからさ。同じパターンが続くとすると、現在の状況はただの混乱期でしか無い。状況は徐々に収束していき、その過程で現在のメジャーブランドの多くは退場していくことになるだろう」
「圧倒的強者でも、10年後は無くなっている可能性があるわけだね」
「まあ、そういうことだ」
「それはGoogleが消えて無くなり、マイクロソフトが復権するという未来予想と考えていいの?」
「そうじゃない。ブランドの多くは淘汰されて消えるだろう、という予測があるだけだ。どのブランドが生き延びるかは、それこそ神のみぞ知るだよ」
「そうか」
「ただ、昔の混乱期を乗り切った経験のあるMSやAppleは生き延びる可能性が高いかもしれない」
「乗り切るための方法論を知っているってことだね」
「でも社員の大多数は昔を知らないと思えば、アドバンテージは無いかも知れない」
「ぎゃふん」
「そういう意味では、こちらもこの状況を乗り切る方法論を(技術的な意味でも)いろいろ知っているぞ。ロートルをなめるなよ」
「この状況に不安があれば知恵を借りに来いってことだね」
「そうだ。たとえば、Javaみたいに仮想マシンで機種の差を吸収するなんて方法論、Javaが影も形も無い昔から知ってるぞってことだ。ついでに、それが普及しなかった理由もね」
「他には何を知ってるんだい?」
「iPhoneなんて影も形も無い頃から、移動体通信は知っている」
「スマホの初めてはiPhoneじゃないってことだね」
「それどころか、通信するだけならコンピュータなんて無い時代から行われている。アマチュア無線のハンディ機で移動中に情報を交換するなんて、パソコンが普及する前から当たり前。トラック野郎の違法CBの電波がラジカセに入り込んでガンガン鳴るなんて、日常茶飯事だったりな」
「嘘。ラジカセにそんな電波の受信機能があるの?」
「無い。でも入り込んでくる。電波障害だ。いわゆるアイってやつだな」
「じゃあ、話をまとめてくれよ」
「そうだな。今の時代、本当に目新しいことは多くない。たいていは反復だ。反復ということは、だいたい結末が読める」
「100%確実な予測ができれば、楽でいいじゃん」
「100%は無理だ。それに、ほとんどのブランドが淘汰されるだろうという予測は、誰が勝つかをなんら教えてくれない」
「ぎゃふん」
「ただ、何通りかのパターンに予測は収束できて、たいていはその範囲から逸脱しないから驚かない。それだけだ」
「予測を覆そうと当事者ががんばる可能性は無いの?」
「たいていは、当事者が自らの行動が反復に過ぎないとは思ってないからな。自分は賢く画期的なことをしていると思い込んでいるが、実際は無自覚な行動が昔と同じパターンにはまってしまう」
「じゃあ、昔と決定的に違うことって何?」
「通信とコンピューティングの連携だな」
「なぜ違うの?」
「昔はNTTではなく電電公社が存在し、通信が自由化されていなかったからだ」
「そうか」
「でも、自由化後のパソコン通信時代の反復になっているだけ、という事例もあるから注意が必要だぞ」
もっと聞かせてよ §
「話はこれだけってことは無いだろ?」
「うん。もっと先まであるよ」
「聞かせてよ」
「ここから先は有料だよ」
「えー」
「ネットの世界はなんでも無料なんてアホな妄言を信じてるのかい?」
「みんな無料じゃないか」
「だったらドメイン名とかグローバルIPアドレスとか確保してみろよ。無料でできるか?」
「そ、それは確かに有料だけど」
「ネットには無料のサービスも多いが、だからといって『何も支払っていない』と思い込むのは間違っている。無料の代価として何を奪われているのかに無自覚な人たちは、きっと永遠に何かを奪われ続けるのだろう」