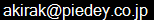実際に以下の方法で塗っているアーガマ作例 §

水性ホビーカラーの問題 §
水性ホビーカラーには以下の問題がある。
- 乾燥が遅い。乾いたと思っても表面だけで触ると手に付く場合がある
- 塗装皮膜が厚めになる
しかし、偶然にも有効な対策に気づいたのでメモ。
やり方 §
- 筆に水をたっぷり含ませる
- その後、少量の塗料を筆に含ませる
- そのまま大面積を一気に塗る
- すぐ乾く
- 生地が透けることが気になるならまた同じことを繰り替えす (すぐ乾くからそれほどは待たされない)
問題の原因 §
シンナー系の塗料よりも溶剤の揮発が遅い……というのは本質的な問題ではないような気がしてきた。
おそらく、塗装皮膜が厚めになった結果、表面が先に乾燥して固定化し、それがまだ乾燥しきっていない内側の塗料の乾燥を妨げることが乾燥の遅さの主原因ではないか。また表面が先に固定化することで、繊細なモールドなども隠れがちになってしまう。そのことが、【塗装皮膜が厚い】という印象を後押ししているのではないか。
対策の指針 §
この場合、対策の本質は塗装皮膜を薄くすることではなく、塗料の濃度を下げることではないか。そもそも水性ホビーカラーは少量の塗料をのばして薄く塗るのがあまり得意とは思わない。それよりも、濃度を下げてしまえば普通に塗るだけで自然と薄塗りになる。塗料と塗料が結合して皮膜を形成できず、自然と塗料がプラに食いつくようになり、繊細なモールドも埋めにくくなる。
濃度の調整 §
大面積を伸ばす場合はこの方法で良いが、小さな面積に塗料を乗せるような塗り方をする場合もある。その場合、塗料は勝手に広がると困るので、濃いめの方が良い。その場合の塗り方はまた別である。
水か薄め液か §
この方法を使うと、塗る際に塗料を希釈する液体として水か薄め液かを選択できる。しかし、この方法で塗ると自動的にその液体は塗料で汚れていくことになるので、高価な薄め液を使うと勿体ない。実際に塗ってみて、筆洗い用に用意した水で十分であった。これならすぐ交換できて値段も安い。
予め希釈しておく方法はあまりお勧めではない。その場で濃度の調整もできないし、塗料が大きく重くなってしまうからだ。
(塗料が堅くなりすぎて塗料瓶そのものを希釈する場合は薄め液の方が良いと思う)
垂れる問題 §
水分を含ませすぎると、塗った箇所から水が垂れてはみ出すという問題が起きる場合がある。流れ落ちるほどの水分はティッシュなどに吸収させて、そこは流れないように配慮した方が良いだろう。
本来は最初から適量の水分を判断する方が良いのだが、意図しない量が乗ってしまうこともある。
感想 §
プロとマニアはラッカー系で塗ると思うが、素人は素人なりに水性ホビーカラーを極めて行こう、と思った。たぶん、彼らとは別の世界に行ける気がする。また、家族の「臭いのいや」対策として、行かねばならないのだ。