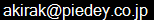「世界初のパソコンは何か」
「その場合のパソコンの定義とは? マイコンとの関係は?」
「それにも依存する頭が痛い問題だが、一応、そこを曖昧に捉えるとMITSのAltair 8800が始祖かと思っていたがそうではないらしい。それ以前にもいろいろな製品が存在したらしいと知って奧が深いと思ったものだ」
「なるほど」
「しかし、日本初のパソコンはもっと混乱が著しい」
「どうしてだい?」
「こんな記述をWikPediaに発見したからだ」
なお、本機が国産初のパソコンという解釈もあるが、「パソコン」という名称(商標)に関してPC-8001が初という意味であり、より広義のパソコンという意味での完成品筐体型マイコンシステムとしてはベーシックマスターが国産初である。またNEC関連に限っても、COMPO BS/80という前例がある。
「これはおかしい話ではないか?」
「うん。実は2つの意味でおかしい」
「2つとは?」
「まず、【より広義のパソコン】という言葉の意味が曖昧すぎて何を言っているのか分からないこと。もう1つは、【完成品筐体型マイコンシステムとしてはベーシックマスターが国産初】ではないこと」
「最初の話はどこが問題なんだい?」
「そもそも定義も無く【より広義】と何でも包含できしまい、何を含めるのかはもう本当に書き手の判断次第になってしまう。詐欺的な用語の使い方だな。しかも、続きの文章を見ると文脈的に【より広義のパソコン】とは【完成品筐体型マイコンシステム】と読めるが、そんな定義は見たことが無い。WikiPediaのパーソナルコンピュータの項目でも以下の様に記述されていて、【完成品】【筐体】は条件に入っていない。逆に【個人によって占有される】というニュアンスがどこにもない」
パーソナルコンピュータ(英: personal computer)とは、個人によって占有されて使用されるコンピュータのことである。
略称はパソコンまたはPC(ピーシー)。
「けっこう【俺がこう思うからこれが正しい】的な雰囲気が出てきたね」
「かなり手前勝手な理屈で書かれているように思えるよ」
「いちいち突っ込まない方がいいんじゃないか?」
「放っておくとトンデモ定義が一人歩きするからな。それは困るので批判しておく」
「分かった。ではもう1つの理由について説明してくれ」
「【完成品筐体型マイコンシステムとしてはベーシックマスターが国産初】ではない」
「その意味は?」
「アスターインターナショナルのコスモターミナルDとかソードの製品があるからね。単に完成品を売ったというだけの話ならそれこそいくらでも。TK-80が作れないから完成品をくれ、という話はいくらでもあったが、ケースに入れて完成品を納入したケースも山ほどあったろう」
「大手メーカーの話に限定している……ではないの?」
「大手どころではない超大手の日立NECレベルが発売しないと歴史にカウントされないとしたら日本全国の超大手以外の企業はみんな怒るぞ」
「えー」
「しかも、コスモターミナルDといえば月刊ASCIIレベルのメジャー雑紙のカラー広告を出しているからな。無名ということはあり得ないし、大手が進出する以前の業界では割と名が知れたプレイヤーの一つだろう」
「値段が高すぎて個人で買えないとか?」
「あのねえ。ビジネスでまともに使おうと思ったらPC-8001だって個人で簡単に買える値段にならない。本体だけなら¥168,000だけどね。これってプリンターもフロッピーディスクも何も含んでいないから。ビジネスにはそれらが不可欠だが、それらを揃えると簡単に50万以上飛ぶ」
「今と違ってネットワークがないのでプリンターが不可欠なんだね」
「そう。それに周辺のいろいろなものやソフトも揃えると簡単に百万を超えるぞ」
「でも、大多数の人はPC-8001の本体だけ買ったよね?」
「ゲームぐらいならできるからな」
「それは実用システムじゃねえ!」
「逆にBASIC MASTERの初期のモデルはオプションにプリンターはあってもフロッピーディスクドライブは無かったはずだ。しかもBASICは整数型。それでまともにビジネスに使えると思うなよ。あれとPC-8001は同列に比較できない」
「とても実用にはならないわけだね」
「あれはホビー用。今のような感覚でパソコンと呼べるようなものではないと思うよ。まあPC-8001も本体だけならホビー用に毛が生えた程度だけどね」
「それでも、BASIC MASTERが日本初のパソコンと呼ばれるようになったのは?」
「偽史だろう。トンデモだよ。インチキ臭い」
「では、PC-8001は日本初のパソコンなのかい?」
「実はそこにも微妙感はある」
「微妙感とは?」
「確かに、箱には堂々とPersonal Computerと書かれているがパソコンとは書かれていない」
「えー」
「しかも、PC-8001全盛期、PCはPC-8001という機種の略称でパソコンの略称扱いではなかった」
「PC-8001がPCで、MZ-80KがMZと呼ばれた時代だね」
「パソコンがマイコンを置き換える用語として定着するのはもっとあとの時代で、PCがパソコンの略称として定着するのは更に後の時代のような気がするね」
「じゃあPC-8001が発売された頃、Personal Computerとは何だったのだ?」
「一部の格好を付けたい人たちがマイコンの格好いい言い換えとして使っていただけで、大多数は意味不明だったのではないか」
「えー」
「おいらも最初は意味不明だった」
「おまえもか」
「そもそも、月刊ASCIIに【Sol-20こそアラン・ケイが唱えた真のPersonal Computerではないか】的な文章があってもどれだけの読者が理解できたか疑問だよ。大多数はアラン・ケイの名前も知らなかっただろう」
「じゃあ、PC-8001の箱に書かれたPersonal Computerの文字は何だったのだろう?」
「かっこいい模様と受け止めた人が多かったのではないか」
「つまり、Personal Computerは当時の生きた用語ではなかったわけだね?」
「そう思うよ」
「つまり問題はなんだい?」
「当時の感覚でものを考えずに今の感覚だけでものを見て、【パソコンのように見えるからパソコン】と言っているだけで、当時それが何と呼ばれていたのかという感覚が欠落している。これは歴史研究としては失格」
「その失格の情報が【事実】として世間に出回ってしまうわけだね?」
「まあ、そんな事例は他にも一杯あるけどね」
「酷い時代になったね」
「昔からそうだったとも言える」
「ぎゃふん」
「昔から、インチキ情報、俗説が出回って信じられてしまう事例は多かったね」
オマケ §
「この問題がこんな泥沼になる理由はなんだい?」
「たぶんね。パソコンはマーティング用語で工学的な意味での定義が存在しないから」
「なるほど」
「だから言った者勝ち、広めた者勝ちになってしまう」
「そこがマイコンとの違い?」
「マイコンも怪しい。Micro Computerの略ならともかく、私のコンピュータ(My Computer)と言ってしまうと定義も何もない。これは俺のだ……と言えるのなら何でもマイコン扱いできてしまう」
「どんなことを言ってもいいわけだ」
「しかし、それは当時のリアルタイムの話だ」
「えっ?」
「歴史研究という観点から言えば、研究対象の時代に流通していない用語を勝手に創作しちゃいかんよ。同様に、今使われている用語を昔に当てはめちゃいかんよ」
「そこが最大の問題だね」
「歴史のイロハだけどな」
「ぎゃふん」