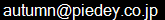「わはっはっは。総統も総統冗談がお好きで」
デスラーが不快そうな顔で椅子の肘掛けのボタンを操作する。
床が開いて消えていく話者。
そして、デスラーいわく。「ガミラスに下品な男は不要だ」
一同、「デスラー総統万歳!」
というのは、デスラーが残忍な独裁者であることを印象づける有名なシーンですが。
あらためて疑問が出てきます。
- 下品な男を謁見室(?)に入れるほどデスラーは寛容だろうか?
更に疑問が出てきます、
- デスラーの真意も分からない愚鈍なヒスを副総統に取り立てているのはなぜか?
- 反乱はカットされただけで予定されていた (ひおあきら版にはある)。反乱があり得るほどの敵対者のパワーがなぜ温存されているのか
- ドメルは誰もが有罪としてデスラーの意志に反するのはなぜか
- 新たなる旅立ちで、誰もいない空のガミラスに戻るのはなぜか
- ガルマン・ガミラスもシャルバート教徒が入り込んでいるのはなぜか
実は不安定なデスラーの権力構造 §
デスラーは残忍ではあるが、独裁者ではなく、国家は合議で動く……と思うと辻褄が合います。つまり、デスラーとは「統一国家を成立させるための旗印」として戦った男であり、彼の功労の大きさゆえに彼が元首になり、敵対者を抑圧する必要もあったのでしょう。しかし、勝利の戦功を示す者は多く、彼らの存在をデスラーは否定できません。
つまり「敵と味方」という分け方は不十分であり、実際は以下のようになると思われます。
- ガミラス体勢の敵
- ガミラス体勢の味方でデスラー派
- ガミラス体勢の味方で別の派閥
しかし、ガミラスの壊滅で、「ガミラス体勢の味方で別の派閥」も瓦解します。ガミラス艦内には、その派閥の息が掛かった艦や兵士もいたでしょうが、トップを失って混乱していたのでしょう。そこで、建前上の独裁者であるデスラーがそれらを統率して部下としたのでしょう。
従って、油断できない白色彗星やヤマトとやり合っているヤマト2の世界で、共通の敵を持ってデスラーは彼らを統率できます。しかし、戦線を離脱した時点で敵がいなくなります。そこで、既に滅んだ母星を部下達に見せることで統率するという目的を持って、わざわざ大マゼラン星雲に戻ります。
ここで、おそらくデスラーの独裁は完全に成立したものと思います。
しかし、大多数の戦力を失い、ガルマン民族を解放する戦いへの転戦します。そこで、勝利にあたっては戦功のあったガルマン民族を否定できない状況があったのでしょう。シャルバートの影響を受けたガルマン民族も参加して戦ってくれたのでしょう。そこで、デスラーの思惑と実際のガルマン民族には認識のギャップが生じて、ヤマトもガルマン艦隊に襲われてしまうわけです。
しかし、完結編でまたデスラーは帝国を失います。
まとめ §
- デスラーは戦争が好きである (くだらぬ飲み物で邪魔されたくないぐらい好きである)
- デスラーは冷酷な性格である (勝利のために味方が死ぬことは何とも思わない。たとえ大帝からお預かりした大切な駆逐艦であってもだ))
- デスラーは潔癖性である (下品な男は許せない)
- デスラーは反逆が嫌いである (シャルバート教徒などは我慢がならない)
しかし、戦争が好きであるがゆえに戦争への協力者も迎えていれて戦い、勝利を得るものの、そうやって成立した帝国での影響力はどうしても限られたものになります。自分1人で得た勝利ではないので。しかし、デスラーにとって帝国とは「大好きな戦争の成果物」であり、いわばトロフィーのようなものです。そのトロフィーをぶち壊し、終わったはずの戦争を再開してくれる相手は、デスラーからは歓迎すべき相手です。
つまり、ヤマトでありそれを代表する古代であるわけです。デスラーはヤマト2で敵をヤマトから白色彗星に切り替えますが、やはりヤマトを倒すより味方にしてもっと別の敵を打倒する方が面白いと気付いたのでしょう。帝国などどうでもよく、戦争そのものの面白さを追求すればそういう考えもあり得るでしょう。
しかし §
やはり最も驚いたのは、釣りバカのアニメを見ているときに、語尾が「ですら」の男が出てきたときですね。デスラー総統万歳、と反射的につぶやいてしまいましたよ。あまりに、総統を思い出させるのですら。