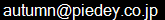以下は、普通の良くあるアニメのパターンです。
- 「敵が出た」→「巨大ロボに乗り込むぞ」→「戦うぞ」→「帰ってバタンキューだ」
以下は、ACE COMBATシリーズのごく大ざっぱな流れです。
- 「ブリーフィング」→「戦うぞ」→「デブリーフィング」
さて、この差はいったい何でしょうか?
つまり、ブリーフィングルームという一種の「会議室」を経由している作品に対して、よくあるアニメはそれを経由していないことを意味します。
実は、ヤマトは大事の前に主要スタッフが集まって説明と意思疎通を行うシーンがあるという意味で、優れているわけです。単に「XXに敵が出た」だけで飛び出す作品とは情報量の厚みが違います。真田さんが「ワープとは」と説明したり、危険だが船団をブラックホールで加速させようと思うが、特に反論はないことを確認するとか、そこにドラマもあります。
どうも、「西崎さんの会議好き」という人もいるようですが、マイナス面だけではなく「主要メンバーが顔を揃えることの効能」についての描写をより的確にする効能がもしかしてあったのかも?
ちなみに、主要メンバーを集めて説明を行うシーンがあるアニメはそれほど多くなく、、まして専用の部屋があるケースはもっと少ないような気がします。しかし、そこで説明してくれるから視聴者もワープや波動砲を理解できるというものです。説明台詞で不自然に話すよりも、ナレーションでお茶を濁すよりも、こういう説明の場が当然あってしかるべきという認識で話を進めた方が良いのだろうと思います。
ちなみにワープはアニメを見て分かったけれど、ミノフスキー粒子はアニメ雑誌を見て始めて意味が分かった気がします。
オマケ §
「突然思い出したんだけどさ」
「なに?」
「会議シーンって、たとえば映画イノセンスにもある」
「それで?」
「やはり会議シーンのおかげで映画内の状況が分かりやすく要約されてくれた感がある」
「そうなのか」
「作中の登場人物が他の登場人物達に向かって状況を要約して説明してくれるシーンはやはり見ている側にも有り難いと思うな」
「そういう意味で、実は会議って重要なのかもね」
「会議シーンでアニメを分類することに意味があるかも」
「ほう」
「たとえば、兜甲児はパイルダーで光子力研究所に来て、そのままパイルダーを降りることなくマジンガーの頭部にドッキングして出撃できてしまう。これって、あまりに安易すぎないか?」
「仲間がいてチーム戦をするなら、それでは意思疎通が不安だね」
「まあ、仲間を前座のやられ役だと思えばどうでもいいのだろうけどね」
「それは、ちょっと笑えないかも……」
「ただ、会議室で作った映画はつまらないという説もあって、本当に会議が良いのかは分からない」
「そうそう。注文を付けた偉い人にだけ分かる自己満足になってしまうか、あるいは表面的に注文を満たす当たり障りのない映画になってしまう」
「でも、きちんとプロが会議をやって合議で作ったシナリオで面白いこともある」
「矛盾したことを言ってるね。それで結論は?」
「分からん!」
「えー」
「もっと映画をたくさん見て経験を積まないと」
「って、映画をもっと見たいだけかい!」