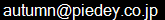「待ってい~る~(待ってる)、待ジャイアンツファンは、待っている」
「おいおい。そういえば前にちょっとプロ野球の話をしていたけど」
「はいな」
「侍ジャイアンツなんて見てたの?」
「うん。再放送だけど」
「奇跡だ」「奇跡だ」「奇跡だ」
「で、後楽園球場は?」
「でかい鯨に見える」
「それは本題ではないから横に置くとして」
「あれ、最初は待ジャイアンツと読んでいたけどね」
「侍と待……、似てるけど」
「でも本放送は見てない。今は芸術映画のプロデューサをしているらしいE君から面白いと教えられて再放送を見始めた」
「それで?」
「鉄の左腕が折れるまで見ていたよ」
「それはないない」
「あとね。旧ルパンが面白いと教えてくれたのもE君。さらに、永遠にジュラ編が掲載された本を見せてくれたのもE君。だから、永遠のジュラは持っていなかったけどリアルタイムで読んでる」
「へえ」
「あと、男おいどんとか、野球狂の詩とかのコミックも見せてくれた。突然、好きなプロ野球チームは東京メッツとか、9番ライト甚九寿とか言えるのはE君のおかげ」
「水原勇気じゃないのね」
「それはもうちょっと後の登場人物。いちばん当時好きだったのは甚九寿のエピソードだった」
「それで?」
「問題はヤマトだ」
「うん」
「ヤマトのTVシリーズは新聞のテレビ欄で、第1話放送の日の朝に発見した。燦然と輝く宇宙戦艦ヤマト文字だ」
「そうだね」
「でもチャンネル権が奪えず、モノクロTVで見る羽目に」
「赤い地球が分からない悲劇がここに」
「しかし、実はヤマトとの出会いはその日ではないのだ」
「えっ? だって第1話放送の朝でしょ?」
「実は放送に先立って学習雑誌に小説が掲載されていたのだ。詳細はもう忘れたが」
「ええっ!?」
「そこに、でかでかとヤマトのイラストがあったのだ」
「なんと」
「これが正真正銘、最初のヤマトとの出会い」
「それもまた壮絶な」
「そして、それをわざわざ見せてくれたのも、何を隠そうE君なのだ」
「なんと!」
おそらくWikiPediaに記述があるこれのことだと思われる
絵物語版 アニメ放送と同時期に「小学五年生」で連載。藤川桂介構成・文。
「でも、そのときははなからバカにしていたのだ」
「え? E君がせっかく見せてくれたのに?」
「そう」
「なぜなの?」
「第3艦橋が寄り添っている宇宙船に見えたし。それに」
「それに?」
「裏切られるのに馴らされすぎていたというのもある」
「その裏切りってなんだい?」
「壮大なワクワクするような話も最後は着ぐるみ格闘とかね」
「ワクワクが小さく萎んでしまうね」
「時期的に矮小化されたウルトラなんかとも一致するしね」
「怪獣映画もつまらなくなった時期だ」
「怪獣などいらん。もっとタックファルコンを写せ! 超獣と言い換えたって要するに同じじゃないか」
「でも、ヒロインは南ちゃんだぞ」
「お子様には関係なかったのだ」
「なるほど、だからウルトラマンエースよりエースコンバット」
「でも、あのとき番組表のヤマトを見て一発で吹っ飛んだ」
「なぜ?」
「学習雑誌掲載とテレビでは本気度がまるで違うからね」
「だから?」
「テレビ番組表に名前を見た瞬間にワクワク期待した」
「でもチャンネル権はもらえなかった」
「なので、2階に突撃したのだ。そこにモノクロTVがあったから」
「そこで、打ちのめされた」
「超弩級宇宙戦艦6、巡洋艦8、護衛艦多数、高速接近中!」
「明らかに子供だましではない」
「まってくれー がしゃん」
「これがヤマトファンの子供ができあがった瞬間だね」
オマケ §
「それで、ヤマトと同時期のウルトラといえばレオなんだけど、なぜエース?」
「タックファルコンと言いたかっただけや」
「なぜ?」
「本当なら、タックアローの搭載とか、いろいろ見せ場がありえた筈だと思うんだ」
「でも主役になれなかったメカだね」
「セブンの時代なら、ホーク1号はセブンを食いかねない魅力と人気があったと思うが、この時期にはもうメカには無い。絶対に怪獣に効かないワンパターンの花火を打ち出すだけ。ペダニウムランチャー搭載のペンドラゴンとは存在感が比較にならない」
「じゃあ、ウルトラなんてもうダメ?」
「でも、レオのドラマはけっこう良かったと思うよ。ウルトラ戦士でもないのに戦う羽目になってセブンに鍛えられるというストーリーも良かったと思う。そもそも、レオといえばウルトラマンレオであって、西武ライオンズではない世代だし。かといって、ジャングル大帝の世代でもないし」
「そういう世代だね」
「あと、マックといえば、マクドナルドではなくてこれ」
「でも、MACになるともうメカは添え物で、あまり印象が残らないね」
「ホーク2号ならすぐイメージ沸くのに、マッキー2号はすぐ分からないし」
「それで?」
「だから、好きなメカはずっとあったのに、帰マンのMATジャイロあたりで打ち止めになって、タックファルコンは好きというレベルまで行けず。ホーク1号とかゴッドフェニックス級の怪獣抜きでも酔えるメカを求める心情が、ヤマトにジャストミートしたのかもね」
「なるほど」
「でも、今から考えればタロウのTのロゴとか、格好いいよね。あえて、ウルトラの父とか母とかタロウとか言っちゃうけど、そこでTのロゴを格好良く見せるダサカッコいいセンスが当時は理解できなかった気もする」
「歌詞も、ウルトラマンナンバーシックスだしね」
「プリズナーナンバーシックスじゃない」
「アステロイドシックスでもない」
「それは関係ない」
「だからさ。キン肉マン・タロウじゃない!ってギャグがいいんだよね」
「じゃあ、センスがあればタロウで満足できたのだろうか?」
「いいや。やはりメカ成分が足りないよ」
「メカさえ出ればいいの?」
「そうじゃない。今なら分かる。やはりメカを使いこなす人間こそが重要だ」
「なるほど」
「だから、極端なことを言えば、メカ抜きの野蛮人の冒険話でも十分に楽しめる。人間さえしっかり描かれていればね。しかし、ウルトラ戦士や怪獣は人間ではない。感情移入できない」
「感情移入してる人もいるじゃない」
「オレはできない。それだけ」
「だからやはりヤマトか」
「熱い友情が、だけど分からない鋼鉄の塊だからいい」
「友情が分かるのは古代と島でいい」
「いいわね、男の人って」
「で、悪は打たなくていい」
「ヤマトは戦うために蘇ったのではないからね」
「だから、おまえの恋人か、ゆるせ古代と言ってもらえる」
「大帝からお預かりした大切な駆逐艦でヤマトを攻撃した人なのにね」