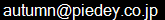「宇宙戦艦ヤマト全記録集TVシナリオ編」を全て読み通した訳ではありませんが、あちこち見ているうちに分かったことがあります。
- シナリオは割と忠実に尊重されている
- しかし、修正箇所も多い
- 修正には、合理的な理由が推定できるものも含まれる (例、ホワイトドッグ隊のカットなど。別の隊を出す時間も理由も乏しい)
- しかし、あまり合理的ではない修正も含まれる (古代守を宇宙パトロール艦乗り組み→宇宙パイロットなど)
- シナリオの宇宙艦はあくまでフネのイメージで一貫している
- フィルムはむしろ航空機である
- シナリオがそのような解釈に適応したことはなく最後までフネのイメージであり、ホワイトドッグ隊も出てくる
さて、このように考えると、どうも「シナリオ対演出」という部分に対立のラインがあるように見えてきます。
ところが、松本零士先生と藤川桂介先生の仲が悪いという話は聞いたことがありません。むしろ、マリンスノーの伝説のころ、西崎さん抜きの仕事で意気投合しているようなムードすら感じたぐらいです。
更に話が込み入ってくるのは、藤川桂介先生の経歴を調べると西崎さんに関連するアニメの仕事も多いことが分かります。
以上から見えてくるのは、むしろ藤川桂介先生は中立であり、中立の立場でシナリオを書いているということです。
具体的に言えば、以下の2点です。
- シナリオのイメージがフネであることは、そのようにして発注されたというだけでのこと
- 書かれたシナリオが演出家によって改変されるのは日常茶飯であり、それは目くじらをたてるようなことではない。シナリオライターは自分の仕事を貫徹するだけである
アニメにおけるシナリオの役目は作品のいかなる部分を作成することでもなく、最初に話を始めるための骨格を提供することだと思うなら、それもありでしょう。
つまり、藤川桂介先生本人はおそらく海派であろうと思いますが、それほど強くそれを打ち出してはいないことになります。
その先を考える §
しかし、問題はその先です。
もし、「シナリオはちょっと違うよ」ということなら、途中からシナリオはフィルム版に近くなっていったはずです。しかし、論調が最後までぶれていないということは、実は「そのことを望んだ誰かいた」ということになります。
その「誰か」は「ちょっと違う」と思っていなかったことになります。
そして、おそらく「誰か」は西崎さんのような個人ではなく、工程の上流側にいた人たちの漠然とした総意ではなかった、という気がします。だから、「誰か」は複数人である可能性が大きくあると思います。
つまり、上流から下流に流れていく過程で、決定的な改変が行われ、むしろ実際のフィルムの方が「ちょっと違うよ」という感じで思っていた人たちがいたのではないか、という気がします。
従って、「さらば」は実は「第1シリーズ肯定の延長線上」にあるわけではなく、決定的な改変を含みます。つまり、フネのイメージへの痛烈な引き戻しです。だから、映画でほとんど活躍しない艦隊各艦を鬼のようにデザインしまくるという状況が発生します。
その揺り返しとしてのヤマト2では、逆にそうやってデザインされた艦隊各艦を活躍させないために火炎直撃砲が出てきて、艦隊の活躍の場は失われます。その代わりに、活躍するのは空母と艦載機です。つまり、航空機です。
とすれば §
実はその延長線上に「永遠に」も解釈できることに気づきました。つまり、序盤であっさりやられてほとんど印象を残さない無人艦隊とは、ヤマトを航空機として描き直すための必須の手順だったわけです。従って、ヤマトは再び巨大航空機のイメージに戻ります。波動カートリッジ弾1発で敵の宇宙要塞が次々炎上してしまうのは、おそらく艦載砲のイメージよりも焼夷弾1発で延焼していくイメージなのでしょう。
だから、完結編で再びヤマトを飛行機からフネに引き戻す作業が行われます。ヤマトは水上から発進し、護衛に駆逐艦が付きます。爆撃機に駆逐艦の護衛は通常付きませんから、あくまで戦艦であるというイメージです。更に、序盤で上下に煽られながら宇宙を飛ぶヤマトのイメージは、明らかにフネです。飛行機はああいう揺れ方をあまりしません。上下に揺れるのは波にもまれるフネのイメージです。
そう考えると §
なぜ、さらばを期待して2を見てはいけないのか、なぜ新たなる旅立ちの続編を期待して永遠にを見ていけないのか、なぜ完結編は問題も多いのに「まあいいか」と思えてしまうのか、全てに説明が付けられます。
更に、なぜ2520なのか、なぜシド・ミードなのかも何となく見えてきます。
つまり、松本ヤマトの航空機イメージを断ち切るには、より大物を連れてくる必要があり、既にビッグネームとなった松本零士先生を超えるのは海外の大物しかあり得なかったということなのでしょう。
いやまて §
アニメは集団作業であり、すべてのスタッフが機能を背負います。たとえ監督であってもです。
一方、漫画家はアシスタントがいても個人の名前で作品を発表して責任も背負います。
つまり、そういうことではないのかな。
松本先生の世界の常識でいえば、主要な役割を担った作品は、全てを自分でやっていないとしても自分の作品。しかし、アニメの世界では個人所有される作品は通常ありえないので、その理屈は通らないわけです。