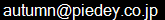「そうか。やっと判ったぞ」
「何が?」
「船舶模型にウォーターラインものというのがある。これは青い台の上に置くと海に浮かんでいるように見せるために船底がないモデルだ」
「うん。ウォーターライン・シリーズってのもあるよね」
「1971年に始まって、それ以前の水に浮かべることが前提のモデルを駆逐した。これはおおむね1970年代以降の流行だ」
「それで?」
「次は東京オリンピックの話題。もちろん、1964年。これを契機に東京の景観はがらっと変わった。高速道路も新幹線もできたし、どぶ川化した水路は蓋をされ、暗渠になった。農地が宅地に転換され、多くの水路が消えた」
「農業用水は不要になったからね」
「あと、神田川などの河川はコンクリートで固められ、容易に水面に降りられなくなったよ」
「1960年代から1970年代の動きだね」
「そして、最後が宇宙戦艦ヤマト、これは1974年だ」
「おっと、ヤマト。全部年代が似てるという話?」
「いや、そうじゃない。互いに関係があったのだ」
「というと?」
「船舶模型は当初水に浮かべることが前提だった。そしてそれは無理な前提ではなかった。日本はかなりの範囲が農地で、そのための水路網が発達し、池も多かった。川にも簡単に降りられた。身近にいくらでも水はあったのだ」
「なるほど。最初のプラモも、潜水艦だったそうだね」
「その時代は知らないが、子供の頃もゴム動力で前進するスティングレイとかシービュー号とか、水ものの模型は多かったぞ」
「なるほど」
「でも、東京オリンピック前後にその前提が失われた結果として、船舶模型は転換を迫られたわけだ」
「そうか、それが畳の上の艦隊、ウォーターラインシリーズなんだね」
「うん。小さくコレクションに向いたサイズで、しかも水無しで並べられる」
「なるほど。でも、それとヤマトがどう関係するの?」
「実は、ヤマトというのはもう1つの水無し対策なんだ」
「えっ?」
「だからさ。戦艦を海に浮かべるのではなく空に飛ばすなら、赤い船底が剥きだしのまま展示されていてもいいわけだ。飛行機と同じだ。今でこそ着陸状態で展示するのが前提のキットばかりだが、昔は飛行状態で展示する台が付いているキットもあったのだ。だから、台座に支持する棒があって空中に浮かんで展示されているのは、宇宙戦艦としてはノーマルな状態なんだ」
「そうか。つまり、水が失われたことに対する対策としてウォーターラインシリーズとヤマトは並列に見ることができるのか」
オマケ §
「というわけで、ウォーターラインモデルは大流行し、その後の圧倒的な主流になった。他のメーカーまで同じスケールや似たようなスケールで模型を出す始末だ」
「そうだね」
「だから、もっと若い世代はウォーターラインモデルしかしらない環境で育っていて、むしろフルハルモデルが珍しいのだ。だから、むしろ大胆な挑戦として、フルハルに回帰しているともいえるが、もう水に浮かべることは前提ではない。あくまでディスプレイモデルだ」
「ヤマトもメカコレのようにコレクション性のあるモデルも出てきたね」
「そのへんは、ウォーターラインシリーズの影響かもしれない。まあ、スケールが統一されているわけではないようなので、並べて艦隊になるかは判らないけどね」
「やっぱりこれが1つの時代なんだね」
「うん。ヤマトの模型という意味では少し遅くなったけど、玩具展開まで視野に入れるとやはり水に浮かべないで済むネタが要求されたのだろうと思う」
「ガンダムのホワイトベースもムサイももはや水に浮かべることが前提になっていないデザインだしね」
「うん。いろいろな問題が結びついて1つの時代になっているんだ」
ゼンマイオマケ §
「だからさ。最初のヤマトの模型はゼンマイだったけど」
「うん」
「でもさ。時代が時代なら、水に浮かべてゴム動力でスクリューをまわして進んだのかもしれない」
「えっ? じゃああの不格好なゼンマイボックスが下に出っ張らないということ?」
「そうかもしれない」
「それは幸せなことだったかもね」
「でも、もう現実的に水に浮かべる模型で勝負できる時代ではなかったのだろう」
スイスイオマケ §
「もし、そういう時代ならヤマトの波動砲発射口は喫水線下に付いたかもしれない」
「なぜ?」
「水に浮かべるとそこから水を吸い込んでウォータージェットで後ろから噴き出すのさ」
「そ、それはなんか楽しそう」
「題してスイスイヤマト」
「重厚感の無い名前だ」
「でも、ゼンマイヤマトよりマシだ」
「確かに」
「CMソングも考えたぞ。すいすいすーだらだった、すらすらすいすいすい♪」
「ちがーう。それは違う歌だ」
オマケ2 §
「今になってやっと思い出した」
「何が?」
「ヤマトの頃、父はプラモを作っていた。その中に船もあった。大和もあったし、イ400もあった。ニチモの護衛艦は何隻もあった。あまつかぜとかたかつきとか」
「それで?」
「それらは全てモーターライズされて水に浮かべて走るモデルだった」
「古い世代のモデルってことだね」
「うん。だからさ、父は風呂場で浮かべてテストすることはできても航走させることはできなかった。風呂は狭すぎたんだ」
「それで?」
「父はマイカーを充電するために毎週日曜に走らせていたが、よく環八と世田谷通りを通って和泉多摩川まで行った。だから、テスト航走は和泉多摩川で行うことが多かった」
「でもさ、かなり遠いよ。そこはもう世田谷区ですらなくて狛江市だろ?」
「うん。だからさ。23区で最もでかかったマンモス世田谷区すら通り抜けて狛江市に抜けないと模型の船を浮かべる水にありつけなかった、という状況があったわけだ」
「ウォーターラインシリーズが流行るわけだね」
「そうだ、あれなら畳の上に並べるだけで格好が付くからね」
オマケIII §
「だからさ。船の模型にグリースという話が直感として分かる最後の世代かもしれないよ」
「スクリューを船外に出す部分に詰めるんだろ?」
「そうだ。水密用だ。ここから水が入ると沈没だからね」
「水に浮かべない模型には存在しないものだね」
「4本スクリューの大和も模型だとグリースを入れる箱が4つもあることになるのだ」
「それは大変だ」
「ちなみに、うろ覚えだが父は4本スクリューの大和の模型にこだわった。しかし、ニチモの1/200はさすがにでかすぎたので、1/350のを作った。メーカーは忘れてしまったけどね。まだ居間のケースの中に鎮座して飾られているよ。最大級の父の遺品の1つと言って良いだろう。1/72の二式大艇よりも九七大艇よりも連山よりもでかい」
「うはは、どのアイテムもマニアックだね」
「1/72の日本の第二次大戦機はほぼ全機種あるはず。1/700の日本海軍の艦艇も。プラモとして模型化されているものはほぼ全種ね。そのうちにオークションで処分するべきかと思うけど、もし引き取りたいという人がいたら連絡を請う。保管スペースのある展示館、博物館などが望ましいとは思う」
「かなりの量だね」
「しかも運搬できるように梱包されているわけではないのだ」
「でも、大切な遺品だろう? 手放していいの?」
「思い出は消えないからな」