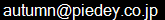「昨日の続きの話を頼むよ」
「うん。というわけで、キネ旬ヤマト特集に泣いた」
「それじゃ分からないよ。話を最初からやってくれよ」
「実はさ。ある日、ふと気付いてヤマト関係の新しい商品があるのじゃないかと思ってAmazonをあらためて検索してみた」
「それで?」
「以下のような発売予定商品があると分かったので、予約を入れた」
「前に出たノベライズと違う文庫が出るのだね」
「うん。でもさ。この2つの発注している際に、妙なことに気付いた」
「なに?」
「キネ旬もお勧めされたのだ」
「それはどういうこと?」
「つまり、キネ旬の2010年 11/15号はキムタクが表紙の実写ヤマト特集であったわけだ」
「なるほど」
「Webではシルエットだけど本物は顔写真が入っている」
問題はどこだ §
「昨日はヤマトの存在感が昔は本屋にあったけど、今はないと述べたね。でも厳密に言うと違った。まるで無いわけでもなかった」
「どう違ったの?」
「ヤマトは、まず本屋のアニメ特撮コーナーに出てくると思った」
「そうだろうね。元はアニメだし、実写版は特撮の一種だ」
「でも、そうじゃなかった」
「というと?」
「今日(執筆日基準)、キネマ旬報を買ってきたけどさ。近所の本屋に1冊だけ残っていたから、運良く買えた」
「それで?」
「キネ旬が置かれているのは映画コーナーで、それは場所が違うんだよ。斜め背後の位置関係だ」
「えっ?」
「だから以下の状況があった」
- アニメ特撮コーナーをチェックしようと視線を向けると必然的に映画コーナーは見えない (人の瞳が背中に付いてないのは、前に向かい生きている使命があるからだ)
- 何となく「宇宙戦艦ヤマトを描いた宇宙ビジュアル」を前提に見ていると、木村拓哉の顔でヤマトは連想しにくい (そもそも木村拓哉は、ヤマトという以前に他の数多くの作品の顔であるし、本人もブランドである)
「なんと」
「盲点だったな」
「そうだね。過去のムックの傾向からは外れるね」
「しかし盲点と言えば」
「何?」
「実は、1年間ほぼ週にに1回映画館に通って映画見ているおいらも、実はキネ旬を買って読んでも違和感無かったんだよな。それも盲点だった」
「そうか、映画雑誌は関係ないと思ってしまったのも盲点か」
「今度のヤマトは映画なのにな」
「じゃあ、ロードショー責任編集という枠を越えてロードショーそのものを読んでも違和感が無い立場というわけだね」
「既に休刊しているらしいけどね」
泣いた §
「これは泣けた。キネ旬のヤマトで泣けるとは思いも寄らなかった」
「どこがそんなに泣けるの?」
「監督もキムタクも記事書いている人も関係者がみんな何らかの形でヤマトの洗礼を受けている人たちなんだよ。だからさ、凄く話が分かるんだよ」
「どんな感じ?」
「こんな感じだ」
- 監督とお会いした時『古代進をよろしくお願いします』と言われ、アンタそれがどういうことなのかわかって言ってるんですか(笑)!?
「ええっ? これ誰の台詞?」
「だから古代進をお願いされた人だよ」
「キムタクが自分でこれを言っちゃったとすると、心情的な目線はファンの目線と同じじゃない?」
「そうなんだよ。古代がキムタクだと聞いて同じようなことを言ったヤマトファンも多いはずだ」
「なるほど」
「しかも、僕がいちばんヤマトを……とは言わない。もっと凄い人が他にいるという」
「そうか」
「でも、本人の熱意も半端じゃない」
「謙遜もあるわけだね」
「更に同じページから引用しよう」
- 現場では"ターゲット・スコープ、オープン"の台詞から波動砲のトリガーをカチッと弾くまで一気に撮ったんですけど、そこでカットの声がかかるはずなのに、ずっとかからない。そのうち後ろの方からグォングォンとか擬音が聞こえてくるので『何?』と思ったら、山崎監督の口から出た擬音だった(笑)。どうも監督の頭の中で、トリガーを弾いた後、波動エンジンが動いて艦首の発射口から波動砲が発射されるまでの画がずっと続いていたらしいんですよ。あそこまで突き抜けると、もう尊敬すべきオタクだなと思いましたし(笑)
「凄すぎて何も言葉がない現場だな」
「別のページの監督本人の言葉も凄いぞ」
- そのときの想いとか全部押し寄せてきて。自分はそれだけ幸運なんだと。それでもういいやと。何を言われても、どんな苦労をしても、『ヤマト』にかかわれるということは自分のなかで大きなことなので、それは結局『喜んでやらせていただきます』ということになりましたね。
「これはもう心情的に良く分かる。何を言われても、どんな苦労をしてもいい。ヤマトをやるチャンスがあればやる。それは大きなことなんだよ」
「なるほど」
「映画監督だから山崎さんには監督としての声が掛かった。おいらは映画業界にいないから声が掛からない。その差はあるけど、心情としては良く分かる。自分が映画監督で三丁目の夕日みたいな映画を撮っていてもやはりヤマトはやる。やるしかない」
「そうか。分かっちゃうのか」
「それはもう激突王ダンと月光のバローネが人間と魔族の境界を越えてわかり合っちゃうのと同じように分かるよ」
「比喩が意味不明だよ」
「ちなみに、他にはブームを表現するのにサタデーナイトフィーバーという名前が出てきたり、デスラーを論じるのに宇宙からのメッセージのロクセイアの名前が出てくるあたり、本当に同じ目線で書かれた記事だなと思う」
「君もヤマトを論じる際に取り上げた映画ばかりだね」
「だからさ。おいらの軸足は既にアニメ雑誌ではなくキネ旬に近かったわけだ。ヤマト特集以外の残りのページはまだ読んでないけど、きっと読んだら意味が分かって楽しめるぞ」
「そうか。すっかり君も映画館の住人だね」
「まあ実際は映画業界にいても、映画監督をしていても、ヤマトをやれるかどうかは宝くじみたいな確率かも知れない。たぶん、そう言えるだけの多数の希望者はいそうだ。おいらと山崎監督の他にもね。だから、ある意味で山崎監督はみんなの代表者でもあると思う」
「西崎死んだらもう永遠にヤマトは作られないとかほざいたアホもいるけどね」
「心情的に作りたい奴はかなり多いと思うよ」
「うん」
「問題はさ。クリエーターが思っただけでは実現しないが、実は実写ヤマトの場合、キネ旬を見るとTV局で映画の企画をしてる人まで損得を越えてやりたいと思った、というポイントが大きい。昔渋谷の東急文化会館で行列してヤマトを見たって」
「あそこで行列か」
「もう無いあそこだよ」
「企画を動かす要の部分でそういう熱意のある人もいるんだ。ヤマトは古代1人の力で動いているわけではないの同じように、ヤマトの映画も様々な人たちの熱意で動いているわけで、本当に個人の我が儘で動く世界じゃないよ」
オマケ §
「というわけで話が終わると思った」
「それで?」
「でもパラパラ見たら編集後記に短いヤマトネタあった!」
「どんなネタ?」
「気になるなら買って読め!」
「そうか、本が売れればまた扱ってくれるかも知れないものね」
オマケ2 §
「小さい写真でさ。佐渡先生(女)が床に座り込んで膝に猫抱えて、同じように座り込んだ徳川機関長に酒を注いでるシーンを見ていたら、やっぱり泣けてきた。佐渡先生が男か女かなんて、実はどうでも良かったのだ。徳川機関長が釣りバカのあの人の顔でも実は関係なかったのだ。佐渡先生と徳川機関長が酒を飲んでいたシーンの有無もあまり関係ない。この絵はヤマトなんだよ」
「違う表現だけど、まわりまわってヤマトの空気感が出ているわけだね」
「そうだ。沖田と古代が艦長室の床に座り込んで一升瓶で酒を飲んでるようなイメージとぴったりだぶるんだよ」
オマケIII巡り愛の戦士達 §
「というわけで、1つ気付いた」
「何を?」
「この特集にガ○ダムに対する言及がほとんどない」
「えっ?」
「歴史として、ヤマトのブームの影響下でガ○ダム3部作が作られたというような話がある等、本当に言及が少なくて、しかもどうでもいい扱い」
「ヤマト以外は扱いが軽いということ?」
「いやいや。エヴァの扱いは軽くない。エヴァと比較してガ○ダムマ○ロスの扱いが軽いのだ。まあ主役はもちろんヤマトだけどね。ヤマトの特集だから」
「そのへんに境界線があるのかもよ?」
「あくまで、主戦場はTVであるガ○ダムマ○ロスがたまに映画を作っても、最初から映画館を主戦場にしている今時のエヴァとは扱いが違うのかもね」
「そうか。キネマ旬報は映画雑誌だものね」
「映画に特別な感情を持つ人が登場して、書いて、読む雑誌だからね」
オマケ実写版 §
舞台挨拶が抽選とは。何回も行われ、ふらっと行って適当に映画見て、一緒にたーかーのーつーめーをやって帰ってくる蛙男商会とはまるで比較にならないなあ。
しかし、ガラガラの劇場で見て1人で納得して終わる予定だったのに、なんか予想以上に盛り上がってる感じですなあ。孤軍奮闘しなくて済みそう。
それから、「映画の設定では全長533メートル60センチ」という説明文は、なるほど!という感じ。公式の設定にはないものの、500m以上のサイズを妥当とする説を唱えるサイトを昔見た記憶がありますが、サイズ上の矛盾を解消する1つの合理的な選択かもしれません。たとえオフィシャルな設定値と食い違っていてもです。というか、マニアックすぎ。半端じゃない。