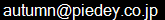「たまげた」
「どうして?」
「ヤマトを語っていて航空宇宙軍史にまで行くとは思わなかった」
「えー」
「ガボーチンさんより、メッセージを頂いた」
名前: ガボーチン
本文:
私も「2199」には驚かされました。しかし、自分の住む辺境では今のところ、上映の予定はないらしいのです・・、もちろん復活編DC版も。
拡大上映を望みたいです。
ところで、マイナーすぎる妄想で恐縮ですが、SF作家つながりと言うことで。少し
前に谷甲州さんの話題が出てましたが、「大ウルップ星間国家連合」って谷さんの「終わりなき索敵」に出てくる「汎銀河連合」っぽいなぁと思いまして。あっ、コレも移動性ブラックホールが出てきますね。となると、途中でいなくなる人物が・・・。
「終わりなき索敵? 君は航空宇宙軍史と言ったじゃないか」
「航空宇宙軍史はシリーズ名。その1作が終わりなき索敵だ」
「えー。そんなにいっぱいあるの?」
「あるある。そもそも初長編の惑星CB-8越冬隊からして、シリーズの1作」
「越冬隊って、まさに南極大陸に隣接した話じゃないか」
「ちなみに、惑星CB-8越冬隊は奇想天外に掲載された時に読んでいる。奇想天外は人からもらったこともあるし、自分で買ってた時期もある。かなり昔の話だな。だから新井素子の大きな壁の中と外とかも、奇想天外で読んだような記憶があるぞ」
「大きな壁の中と外? WikiPediaの新井素子の項目には著作に載ってないぞ」
「あったんだよ」
「それで新井素子にはまったの?」
「というか、あの当時のSF界のアイドルだからな。年若い女性が書いているので、注目は必然だ。中身に青臭い部分があっても、それが若さの証明になっていた」
「ふーん。話はだいたい分かった」
「分かるな! ここでの本題は谷甲州だっての!」
「それで、谷甲州は?」
「ひと味違ったね。アイドル路線では支持を得られない男性小説家群はやはり結果で違いを出さないと評価されない。その点、谷甲州はムードが違った。自分で海外青年協力隊で活動した経験があるからだろう」
「印象に残ったんだね」
「そうだな。もううろ覚えだが、あの当時印象に残るのがSFマガジンの戦闘妖精雪風、SFアドベンチャーの李家豊(りのいえゆたか)、そして谷甲州だね」
「戦闘妖精雪風って、何年か前のアニメだろ」
「原作はかなり古い。1980年代ぐらい」
「へー。でも、李家豊って誰? ぜんぜん無名じゃん」
「アニメファンならみんな知ってる銀英伝の原作者の田中芳樹のことだよ」
「ぎゃふん」
「だからさ。アニメ見て『戦闘妖精雪風って面白ぞ』と言われても、だからどうしたとしか言えない。こっちはとっくの昔に知ってるんだよ。原作を」
「銀英伝も?」
「銀英伝など影も形も無い頃、田中芳樹が李家豊名義でSFアドベンチャーに書いてた頃から、特に注目してたんだよ。他の作家とは文章の持ち味がまるで違った。凄く透明感があった気がする。あとから単行本で読んだらそう感じなくなっていたのは慣れたからだろうな」
「ひ~」
「で、谷甲州は日本沈没第2部を書く遙か以前から注目してたんだよ」
「それって自慢?」
「そうでもない」
「というと?」
「結局、注目してた頃にはほとんど注目している自分が理解されなかったからね」
「えー」
「昔の特撮映画の話しかしない/できないSFファンなんてのがゴロゴロいた」
「ヤマトファンはいなかったの?」
「彼らは囓った程度さ」
「じゃあ、アニメファンの集団に行けば話ができるの?」
「できない。だって彼らはアニメファンだからアニメ雑誌買ってもSF雑誌買わないし」
「ぎゃふん」
話はヤマトに戻る §
「しかし、ここまで書いてはたと思った」
「それは何?」
「戦闘妖精雪風、銀河英雄伝説、航空宇宙軍史。この3つの共通点はなんだ?」
「なんだろう?」
「未来戦闘機ないし宇宙艦ものなんだよな」
「えー」
「描き方にこそ差はあってそこが作家の個性なんだけど、結局モチーフが似通っていて、それらは世に出る背景にはヤマトブームが影を落とす。直接的では無いだろうが、そういう空気を醸造したのはヤマトだろう。良くも悪くもな」
「そうか」
「というわけで、ヤマトから谷甲州まで行けるかという問いにガボーチンさん経由で行けるという答えで終わると思ったら、当時の一群のSF小説のバックグラウンドにヤマトを感じて終わってしまった」
「わははは」
あえて更に過去に遡上する §
「WikiPediaには宮武一貴のページにだけ情報があった」
- 全艦発進せよ!(オール・ファイヤー)SF未来戦記 徳間書店 1978年 (表紙・挿絵)
「これは何?」
「1978年の段階で既に出ていたSF小説のアンソロジー本だ。ミリタリーをテーマにしたSF短編小説集だ」
「1978年。1980年代ですらない」
「しかし、1974年のヤマト後ではある」
「つまりどういうこと?」
「まず、宇宙戦艦などの未来兵器を使ったSF小説の世界はこの時点で既に路線として確立してたと考えられる。その背景にあるのは、おそらくヤマトだ。そもそも、表紙・挿絵が宮武一貴というのが、いかにもヤマト臭い」
「どうして?」
「ヤマトの設定画を一杯描いた宮武さんだからさ」
「ぎゃふん」
懺悔 §
「しかし問題が1つある」
「それはなんだい?」
- 終わりなき索敵→内容をほとんど覚えていません
- 全艦発進せよ!→内容をほとんど覚えていません
「ぎゃふん」
「すまぬ、懺悔する。まさかここで必要になる知識とは思わず忘れてしまった!」
オマケ §
「じゃあ、アニメファンの集団に行けば話ができるの?」
「できない。だって彼らはアニメファンだからアニメ雑誌買ってもSF雑誌買わないし」
「そこにあるギャップが理解されないから、高千穂遙が怒ってOUTでSF論争を引き起こすわけだね」
「うん。そうだ。巨大ロボットが巨大な剣を振り回してチャンバラやってもSFになるわきゃない。巨大ロボットも結局キャラの変種でしかなく、中身はSFじゃなくてチャンバラだ」
「そうか」
「そういう中で、それでもSFにこだわる人たちも少数ながらアニメ界にいて、数は少ないがSF的な要素がアニメに入ることもある」
「たとえば?」
「ヤマトでも異星人が人間そっくりなのはあまりSF的とは言えないが、ビーメラ星人とか冥王星の現住生物とかはSF的なテイストが入ってきている」
「そうか。人間そっくりの異星人は不自然だものね」
「だから、ホーガンの星を継ぐ者とかは『異星人なのに人間そっくり』であることが解き明かすべきミステリーという主題になる」
「そうか」
「そういう意味で、ロケットや巨大ロボが出てくるだけでSFと称する悪い風潮は摩擦を引き起こして当然」
「それぐらい、水と油の世界なんだね」
「そう思ったが、いざ真面目に振り返って検討すると、それでもアニメ→小説SFへの影響の流れを想定できて、興味深いな」
「なぜ想定できるのかな?」
「結局、小説SFへの目配りがある少数のキーパーソンが、少数派ながら重要なポジションにいたからだろう」
「キーパーソンって誰?」
「ヤマトでは豊田有恒はSF作家だが、松本零士もSF小説のイラストを描いていて実はけっこう深い」
「何を描いてるの?」
「いろいろあるが、いちばん分かりやすいのは有名なシャンブロウだ!」
「知らない……」
「ぎゃふん」
「説明してよ」
「『宇宙軍大元帥として命じる。ガ○ャピン、ム○ク。シャンブロウ号で出動せよ!』という内容だよ。嘘だけど」
「嘘かよ!」
「他には、実はガンダムの冨野監督も分かっている。だから、ファーストガンダムはオニールのスペースコロニーから始まる」
「オニール?」
「あれは、スペースコロニーというアイデアを思いついたから偉いのではなく、オニールのスペースコロニーを描いたから偉いんだ。その差は大きい」
「ふーん」
「そしてマクロスの母体はぬえであり、小説SFベースのビジュアルデザイン集団だからな。そもそも、ぬえのパワードスーツだって、もともとはハインラインの宇宙の戦士つまりれっきとした小説SF用のデザインだ。当然分かってる」
「なんで、ヤマト、ガンダム、マクロスなの?」
「アニメびぃ~とでも、さりげなくこの3作品の名前が語れたが、この3作品でおおむねアニメの流れが規定されてしまったからだ」
「そこに小説SFのエッセンスのカケラが含まれたから、そこから小説SFへのフィードバックもあり得たわけだね」
「細い経路だけどな。それはあった。その経路を追いかけてみることも、今となっては無駄ではあるまい」