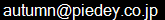「最近は、2世代ドラマが増えていると思う」
「たとえば?」
「最近のライダーの映画には、昭和ライダーも出てくる。お父さん世代も満足だ」
「ウルトラは?」
「ウルトラマンゼロは、セブンの息子だ。息子を見守るセブンは、お父さん世代のヒーローだ。しかも、ゼロと一緒に活躍する3人は、お父さん世代のミラーマン、ファイヤーマン、ジャンボーグAをモチーフとする」
「そうか」
「戦隊でも古い戦隊が全部出てくるゴーカイジャーのような例が出てきている」
「わははは。なんて豪快な」
「ゴーカイジャーがギャバンと共演するとき、ギャバンはお父さん世代だ」
「確かに」
「このような2世代化は、子供に『見たい』と言わせ、パパも見たい方向に誘導する方向で効能があると思われる……が」
「が?」
「実は、ここで非常に特異なのがイナズマイレブンなのだ」
「どうして?」
「子供に人気のイナズマイレブンだが、比較的新しいタイトルであり、パパママを動員するのは難しい」
「そうだね。昔は無かったよね」
「でもさ。やはり2世代化が進んでいるんだ。第1シリーズでは親世代である伝説のイナズマイレブンと試合をするエピソードがあり、後継シリーズのGOでは無印のキャラが大人になって登場する」
「なぜだろう?」
「おそらく、イナズマイレブンだけ2世代化が狙っている効能が違う」
「えっ?」
「ドラマを立体的に構成することが主な目的ではないだろうか」
「立体的とはどういう意味?」
「成長することによって、立場が変わる。視点も変わる。発言も変わる」
「かつての初々しい新人キャラでも、立派な大人になっていればOBってことだね」
「だから、そこで出てくるのは人間の変化と受け継がれる情熱なんだ。無限に誰かがヒーローであり続けることはできない。ライダー1号は永遠にヒーロー扱いされてライダーキックするが、それは本当ならおかしい。しかし、円藤がゴールを守らずに試合を采配する監督になるのは、『人間の変化』を描こうという一種の意欲であるとも言える」
「それは、ウルトラマンタロウにウルトラの父やウルトラの母が出てくるのとは話が違うんだね?」
「そうだ。あれは父とか母とか、役割の固定という誘惑に満ちている。しかし、イナズマイレブンの場合、情況の変化でキャラの立ち位置がどんどん変わる」