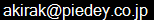20巻p150左下にある魔法世界側ゲート施設全景のイラストは、よく見ると施設外に短い線として人間が描き込まれています。これは凄いですね。省略しないで人間を描いています。
という話題でダラダラと1文を書きます。
絵の教室 §
私が通っていた幼稚園は、卒園後も参加できる絵などの教室を開いていました。そこで、私は絵の教室に小学校6年まで通っていました。そこで、最終的に油彩で描くところまで体験できました。
そこでの体験だと思うのですが、1つとても印象的だった出来事があります。ジャングルジムの絵をクレヨンで描いたときだったような気がします。当時の私は、無機質な工業生産物こそが絵の主題であり、不完全で柔らかい人間は邪魔物だと思っていました。しかし、絵の先生は「こんなもので良いから人間がいる方が良い」といって、頭は丸、胴体は線、手足は線という簡略化された人間を何人も描き込んでいきました。
たとえ簡略化されていようと、人が絵の中に描かれることで「見る者の居場所が絵の中に与えられ、絵を見る印象がグッと良くなる」ということでしょう。
スケールモデルの航空機 §
スケールモデルの航空機模型の世界では、パイロットのフィギュアが重要な意味を持ちます。戦闘機の座席にパイロットが座っているだけで印象が変わります。さすがに、1/144クラスになるとパイロットを作り込むことは難しいのか、付属していないケースもあります。しかし、1/72か、それよりも大きなスケールであれば、パイロットフィギュアは極めて重要です。
それは、なぜACE COMBAT 5の架空機であるADF-01 FALKENが、模型にするとイマイチ面白くないのかという理由も明確に示しています。モニタを見ながら操縦する設定のFALKENにはキャノピーが存在せず、パイロットを見せることができないからです。ACE COMBAT 3のニューコムの機体がハセガワからレジンキットとして発売されたものの、さほど目立つことなく消えていったのも同じ理由かもしれません。
やはり、人が見えることは重要なのです。
鉄道模型の事例 §
鉄道模型のレイアウトを作る上で発生する典型的な問題は、樹木と人物です。
樹木というのは、山を作って樹木を植えようとすると、驚くほど多くの数が必要とされ、模型店で高価な樹木模型を買っていては破産するという問題です。そのため、簡易な樹木の量産方法がいろいろ工夫されています。
人物も同様で、レイアウトに適当な密度で人物を立たせようとすると、驚くほど多くの人形が必要とされます。しかし、模型店で買っていては破綻するし、模型店で調達できる人形はバリエーションも少なく、しかも海外製品は日本の風景に似合わないこともあります。
それにも関わらず、レイアウトには人を立たせることが必要です。なぜかといえば、人が立っていないレイアウトと立っているレイアウトでは、印象が歴然として違うからです。だから、安価な量産方法が工夫されることもあります。
人を使う演出の破綻 §
このように、絵にせよ立体作品にせよ、人をそこに置くことの価値は計り知れないものがあります。
しかし、このやり方はサイズが極端に大きなアイテムを相手にしたときに破綻します。人が小さすぎて表現できなくなるのです。
たとえば、1/700程度の艦船模型に人を乗せることは極めて困難です。身長がせいぜい2~3mmになってしまうからです。
絵を描く場合でも、描く対象物が大きくなると、人を描き込むことが難しくなっていきます。たとえば、広大な施設の全景イラストなどを描く場合、人を描こうとしても画材で描けるサイズを下回ることもあり得ます。
それでも描いたよ! §
20巻p150左下にある魔法世界側ゲート施設全景のイラストが秀逸であるのは、通常なら人を描くことは不可能ということで、建物だけを描いて済ませるであろう状況でありながら、たとえ短い線としてでも人を描いている点です。建物のスケール感は、手前に描かれた船でも表現されているにも関わらず、人も描き込んでいます。
その成果は歴然としています。
空気感と人の存在感のある良い絵になっています。
かといって、何もかも描き込もうとする過剰な詳細主義には堕落していません。描く意味のないディティールはきちんと省略されています。
この徹底的にこだわりぬいた絵は凄いよ!
オマケ・メガロメセンブリアの風景 §
その直後に出てくるメガロメセンブリアの風景は、既にスケール的に人を描けるレベルを超えてしまっています。それゆえに、風景の中に人は描かれていません。しかし、よく見れば窓からその風景を見ている少女達を手前に描くことで、きっちり「人のいる絵」として成立させています。