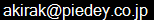あまりにうかつでした。
もっと早く気付くべきでした。
24巻の最後で、フェイトを前にしたネギは、コーヒーを「無粋な泥水」と称します。この台詞にずっと違和感を持っていましたが、やっと解釈が浮かんできました。
銀英伝という前提 §
「無粋な泥水」は銀英伝のヤンを意識させる台詞です。しかし、単に銀英伝が好きなスタッフがいるから使ったネタ、というには重要なシーンで強調される台詞でありすぎます。従って、銀英伝的なものを想起させる、あるいはそのようなムードを作り出すために選択された意図的な表現と見なします。
この場合、ネギはヤンの立場に対応します。
銀英伝的構造 §
このように考えたとき、「全く別の場所からやってきた若きライバル」としてのフェイトはラインハルトに立場に対応します。
とすれば、この構造は以下の未来を暗示します。
- 世界は2大勢力に分割される
- 今はまだ無名のフェイトとネギは、様々な経緯の中で頭角を現し、2大勢力のそれぞれの主導的役割に立つ
対立軸はどこにあるか §
ネギは闇を選び取ったことが明示的に示され、一方のフェイトはベタを使わない「明るい」描き方をされています。そのため、ネギが闇ならばフェイトは光であろう、という想像ができます。
とすれば、2大勢力に分割される世界の対立軸は、「闇」と「光」ということになります。
ナギの居所 §
このように考えると、実は生きているのに姿が見えないナギの居所がおおむね想定できます。つまり、光の道を進んだナギは、フェイト側の陣営にいるわけです。一方、ネギに好意的な人たちは、それと対立する闇の陣営側にいると考えられます。これは、ナギが姿を見せられない理由の解釈となります。
そして、ネギが光の陣営に勝ち続けると、必然的に敵として父=ナギが出てくる構造も暗示させます。
物語のあるべき基本形の1つである「父との対決」がここで実現します。(当然、ネギま!のような高度な作品で、そのような基本形を意識していないわけがない。それを踏襲するにせよ、外すにせよ)
しかし、「帝国の逆襲」の父子対決が「闇の父」対「光の子」であったのに対して、ここでは子供の方が「闇」であり、しかも主人公である点が特徴的です。実現すれば、非常に面白く興味深いことです。ワクワクしますね。
なぜ黄昏の姫御子は「黄昏」でなければならないのか §
この解釈を用いると、24巻のラストシーンがなぜ明日菜の争奪であるのか。そして、なぜ明日菜が「黄昏の姫御子」であるのか、という理由まで解釈可能になります。
つまり、「黄昏」とは「光の世界」と「闇の世界」の中間領域であり、明日菜がフェイトとネギの対立の中間に存在して争奪される対象であることを示します。
であるから、このシーンはフェイト、ネギ、明日菜の3人から構成される必要があり、かつ、フェイトとネギは明日菜を巡って深刻に対立しなければなりません。
そして、光と闇の対立にあって、どちらの陣営にも属さず争奪される対象であるためには、どちらの世界にも属しつつ、どちらの世界にも属さない「黄昏」である必要があるわけです。
とすれば今後は…… §
明日菜はナギが属する光の陣営と、ネギが属する闇の陣営の間で引き裂かれる存在になっていく可能性があります。そして、それこそが「黄昏の姫御子」という名が示す必然的な状況かもしれません。