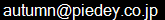以下は思いつきのメモなので、内容を信じてはいけません。
前置き §
今日、2009/09/11はドラクエ9が劇的に変化した日として歴史に残るような気がします。もちろん、ソフトがバージョンアップすることなく、ソフトが持つ意味合いが劇的に変化してしまった、というかなり予測不可能な事態によって記憶の残るような気がします。特にWi-Fiクエストは全く予想もしていなかった展開です。
2009/09/11のトピック §
まず、ヘッドライン的に2009/09/11のトピックを列挙してみます。
- ドラゴンクエスト モンスターバトルロードIIとの「超連動」開始 (これのみ実際には未体験)
- 「Wi-Fiクエスト」スタート
- ドラゴンクエストIX 星空の守り人 公式ガイドブック 上巻/下巻の出版
- リッカの宿屋にバーバラ来訪
- Wi-Fi配信クエスト2つ配信
これだけでは良く分からないと思います。これらは要約すると以下の方向性を明瞭に打ち出しています。
- もう1つのゲームフィールドが現実世界であること (2重のゲーム世界)
- ラスボスを倒すことは物語の終わりを意味しないこと
- 正解が存在しないゲームであること
従って、ドラクエ9のプレイヤーは従来のRPGプレイヤーとは全く違った行動を取らねばならないことが明確に示されたと言えます。従来のRPGプレイヤーは、たった1つの仮想世界に用意されたたった1つの正解つまりラスボスを倒すことを目指して直進し、その他の要素は「長く遊ぶためのオマケ要素」と認識するだけで良かったわけです。しかし、ドラクエ9はその方向性を明確に否定しています。しかも、遅発的に発売後2ヶ月経った2009/09/11になってそれを強く打ち出しています。
以下、この3つのポイントに絞って、見てみましょう。
2重のゲーム世界 §
たいていのゲームは1つのゲーム世界を提供します。たとえば、FINAL FANTASY XI(FF11)は、オフィシャルから行われるアナウンスは「現実世界の開発者、運営者からの言葉」ではなく「あたかもヴァナディール世界から語りかけるかのような口調」を模倣して行われることも多いといえます。現実世界を忘却し、ヴァナディール世界こそが唯一の現実であるかのように思わせる演出の一環と言えます。まして、マルチプレイヤーではない一般のRPGは単一の世界の中で閉じていることが普通です。
これに対して、ドラクエ9は現実世界に対して開いています。すれ違い通信のために現実世界の特定の場所に出向くこともゲームを遊ぶ行為の一部であり、別のプレイヤーが別の世界を持っていることもゲーム内で明言されています。
しかし、それでもまだ、現実世界でプレイする行為は「過剰に熱心なプレイヤーが行う行為であり、やらなくてもよい」と解釈する余地がありました。しかし、2009/09/11を契機にして、その解釈も明瞭に否定されたことになります。
まず、「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードIIとの超連動」は、特定の宝の地図を入手するためには特定の場所に出向かなくてはならないことが規定されたことを意味します。しかし、それはゲーセンで「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードIIを遊べ」という営業的な要請を意味しません。通信アーキテクチャやWeb上の記事などを見る限り、ドラクエ9プレイヤーが集まる場、契機として「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードII」を使うという意図のようです。たとえば、誰が1人が「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードII」で魔王と対戦すれば、近くにいるドラクエ9プレイヤーは全員宝の地図を得られると思われます。つまり、情報交換をしたり、「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードII」で魔王と戦う者を応援したりすることも、意図的なゲーム性の一部だと考えられます。
つまり、現実世界はドラクエ9をプレイする第2のフィールドであり、それは人間と人間の関係としてプレイされることになるわけです。
そして、「リッカの宿屋にバーバラ来訪」という出来事はけしてそれと無関係ではないでしょう。というのは、バーバラが登場したドラクエ6とは、「2つの世界をフィールドとしてプレイするRPG」だったからです。もちろん、ドラクエ6の2つの世界はゲーム内の仮想のもので、現実世界は含みません。しかし、「2つの世界」という構造は似ています。だから、2009/09/11に来訪するゲストはドラクエ6の登場人物である必要があった、と考えることもできるでしょう。
もう1つの現実世界 §
昔、KEY THE METAL IDOLというOVAがありました。この作品は「3万人の友達を集めるためにアイドルになる」という内容で、作中の登場人物が3万人を集めるというだけでなく、実際にこの作品を買うファンを3万人集めようとした、という側面もあるようです。
しかし、この作品が成功したとは言えないと思います。というのは、結局のところ3万人を集めることの意味が、まず発売元の営業的な理由と見えてしまうからです。(実際にはそうでないとしても)
さて、ドラクエ9の「Wi-Fiクエスト」の第1回は、"『ぼうけんのしょをWi-Fiつうしんでおくる』の実行プレイヤー数が9月30日までに50万人達成できるか!?"というお題です。
この遊びは、KEY THE METAL IDOLと比較して以下の点で決定的に優れています。
- 「Wi-Fiクエスト」にはスク・エニに対する追加の支払いが一切存在しない。つまり金儲けの手段とは全く見えない
- 参加することで得られる報酬が明確かつ魅力的である (みごとこのお題が達成できれば なんと! 『ドラゴンクエストソード仮面の女王と鏡の塔』より ゴスロリ僧侶「セティア」を スペシャルゲストとしてリッカの宿屋にご招待! ゴスロリファッションがステキなセティア様がいらっしゃれば きっと素晴らしいコーディネートを伝授してくださるでしょう)
- 1つの目標のために、50万人もの多数が力を合わせたという手応えを得ることができる
50万人は仮想世界の設定上の話ではなく、もちろん現実世界の現実のプレイヤーの話です。その50万人が1つの目標に対して結束して立ち向かうのは、ある意味で空前の規模のゲームといえます。
たとえばFF11のオープニングムービーのラストには無数のプレイヤーキャラクターがずらりと並んで1つの目標に立ち向かうことを暗示するような光景が描かれます。しかし、実際のゲームでそのような展開はありません。他のプレイヤーは獲物を奪い合う敵対者であり、彼らが属する国家も複数存在していてそれぞれが敵対して競い合う存在です。そして、全員で力を合わせて倒すべき敵は実質的に存在しません。
つまり、FF11のオープニングムービーを見て期待して完全に肩すかしを食った、「見知らぬ膨大な仲間達と1つの目標に向かう」という「現実世界」の遊びが、ドラクエ9で初めて達成されたような感覚があります。
ちなみに、この感覚は「50万人」という破格の規模だからこそ実感できるとも言えます。3万人ではなかなか実感できません。
ラスボスを倒すことは物語の終わりを意味しない §
Wi-Fi配信クエストNo.137「悪魔の呼ぶ声」は、実はドラクエ9のストーリーの序盤にあった黒騎士に関する一連の物語の1つの区切りとなるものです。しかも、ラスボスを倒す前には実行できません。つまり、ドラクエ9のストーリーは、一見してラスボスを倒して終わったかのように見えつつ、実際には終わっていなかったことが明示されたのです。
ですから、Wi-Fiクエストの配信が続く限り、「真の終わり」は見えてこないことになります。
これは、完成された攻略情報が少なくともWi-Fiクエストの配信が終わるまで成立し得ないことを意味します。(不正なチート行為を行わない限り)
とすれば、プレイヤー達は一方的に誰かから完成した手順をもらってこなすことはできず、情報を交換しつつ手探りで進めていかねばならない要素が常に入り込んでくる可能性を持ちます。
これは、現実世界の対人プレイを行わねばならない理由の1つとも言えます。
正解が存在しないゲームであること §
「ドラゴンクエストIX 星空の守り人 公式ガイドブック」は本当にワクワクするような本です。モンスターや装備品の大きなイラストが並んでいる点が特に魅惑的です。絵の持つ魅力も絶大です。色っぽかったり、繊細だったり、荒々しかったり。そして、装備品を装備した状態の画面写真が網羅されて並んでいるのも非常に便利です。
そういうビジュアル的な側面が過去の攻略本には無かったわけではありません。しかし、今回は特に強化されているような気がします。
それらが意味することは明確です。
- この本の主要な存在意義の1つはファッションカタログである (ファッションカタログは見ているだけで楽しい)
- ファッションは多様であり唯一の正解はない
もし正解が1つしか存在しなければ、先に正解に到達した者が常に大きな顔をすることになります。しかし、唯一の正解がない世界であれば、そういうことはありません。たとえば、ストーリーもあまり進んではおらずレベルも低いが、かっこいいコーディネートをビシッと決めているプレイヤーが注目される、ということもあり得るでしょう。
つまり、ドラクエ9とは「ゴールは僕が決める」ものであり、誰かに強制されるものではないことになります。ラスボスを倒すことは、ドラクエ9世界の「成人式」のようなものであり、誰でも通る単なる通過点の1つに過ぎないと言えます。その先は自由です。
しかも、持て余すような過剰な「自由」ではありません。いろいろな服を取りそろえ、着せ替えているうちに「あ、これ好きかも」と思える組み合わせに出会えば、それで実現しうるのです。そのときに、「これが僕のゴールだったんだ」と思うことができれば、それが「僕のゴール」です。
感想 §
たぶん、初代のUltimaとWizardry以来のコンピュータRPGの歴史で、決定的にRPGというゲームの質が変化してしまった契機はFINAL FANTASY VIIとネットワークRPGの成立時の2つしか無いような気がします。初代ドラクエが画期的であったのは、PC上のRPGをファミコンに持ち込んだことにあって、ゲーム性そのものが変革したわけではありません。
しかし、ネットワークRPGは実際には成功しなかったと考えます。(詳しい話は割愛します)
その「成功可能な代案」として出現したものが、おそらくはドラクエ9だろうと思います。かつて、FINAL FANTASY VIIがRPGの基本文法をごっそり差し替えてしまったように、lおそらくドラクエ9もRPGの基本文法を差し替えてしまったのだろうと思います。
余談 §
たぶん、「ファイナルファンタジーVII 解体真書」と「ドラゴンクエストIX 星空の守り人 公式ガイドブック」の著者が同じベントスタッフであるのは、意味があるでしょうね。
もう1つ余談を書くと、Wi-Fiクエストには漫画雑誌の読者投稿コーナー的な誰でも気軽に参加できるハードルの低いワクワク感がありますよね。そのあたりのセンスは、やはり堀井雄二だからできること、というべきか?
追記 §
念のために補足すると、ドラクエは伝統的に「プレイヤーが職場や学校で情報交換しながら攻略する」ことを前提にゲームの内容がデザインされています。ドラクエ9でも、攻略サイトがあったり、掲示板で情報交換を行いながらプレイすることを念頭に置いてバランスがデザインされている感があります。そのような考え方の延長線上に、「人と人とが現実世界で結びつく契機」としてのゲームがあるのは当然の成り行きであり、仮想世界で出会うことを前提とするゲームとは一線を画すると感じます。
とはいえ、気軽に持ち出せないWiiで稼働するドラクエ10で同じ方向性は堅持できないと思うので、どうなるかは分かりません。