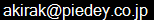「33巻だが、実は一筋縄では行かないことに気付いた」
「なんだい?」
「33巻はリア充という言葉が出てくる」
「うん」
「ポヨさんは『この術はリア充には効きにくい』と言っているが、結局全員に効いてない」
「それは、ネギパーティーはリア充であるという表現なのかね」
「仮にそうだと仮定しようネギパーティーのメンバーは全員リアルで充実していることになる」
「うん」
「でもさ、魔法世界の住人のかなりの割合はリアルじゃないんだよ。実際には実在していないんだよ。魔法で作られた虚構の存在なんだよ」
「えっ?」
「だからさ。魔法で作られた虚構の存在とふれ合う行為は、リアルでは無く、それに充実していてもリア充と呼んで良いか分からないんだよ」
「ちょっと待て。頭が混乱してきたぞ」
「ならば、このリア充には効きにくい術を経由していったい何を語ろうとしているのだろうか?」
リアルの境界問題 §
「更に言おう。この世界観において、魔族は実在しているのだろうか」
「えっ?」
「つまりだ。ネギとクラスメートは実在であると仮定されているが、仮に魔族が実在していないとなると、ポヨとザジは実在していないことになる」
「ええっ?」
「ならば魔族と人間のハーフとはいったい何だろう」
「頭が痛いぞ」
1つの解釈は §
「魔法世界とはネットRPGのようなもので、ネギパーティーの現状はログアウトできなくなっているだけ、というのが自然な解釈だな」
「そうか」
「だからリア充という言葉は、『現在仮想世界にログインしているか否か』ではなく、『ログアウトした先に充実した人生を持っているか』に掛かっているのだろうな」
「なるほど」
「しかし、もう一歩解釈は深くできる」
更なる解釈は §
「まだ先があるの?」
「あるとも」
「それはいったいなんだい?」
「リアルとバーチャルの差は無いということだ」
「えっ?」
「リアルで叩かれたら痛いが、バーチャルで叩かれてもやはり痛いよ」
「そりゃ痛いかも知れないけど。でも現実じゃないだろ?」
「現実じゃ無くても痛いのだ」
「じゃあ、いったいリアルとはなんだい?」
「もしかしたら、異質なる他者と向き合う意志こそがリアルなのかも知れないぞ」
「なんだそれは」
「虚構のキャラクターだろうと現実の人間だろうと関係無い。異質なる他者と向き合う覚悟があって、それに対する手応えがあれば、それはポヨの言うリア充にあたるのだろう」
「では非リア充ってのはどうなるんだ?」
「この条件に当てはまらないのが非リア充だ」
「具体的には?」
「指さして返事をされる覚悟が無く、顔も見せないし名前も伏せる。仮名すら名乗らない。仮名を名乗れば、『XXという仮名を名乗った奴、出てこい』と指をさせる」
「名無しさんの世界だね」
「意外と今時のオタクに迎合しているようで、実はその逆かもしれないぞ、このネギまという作品は」