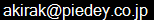「実はさるブログではたと立ち止まってしまった」
「なに?」
「以下だ」
(12) 『放課後ウェディング』を無料公開しました!(β2) - (株)Jコミの中の人より
女性向けの漫画ですが、男が読んでも面白いです!(^^)
「これが何か? 性別を超えてアピールする要素があるならそれはいいことじゃないか」
「そうじゃない」
「じゃあ何?」
「おいらの子供の頃は、以下のように言われていたのだ」
- 男子はみんなキャンディ・キャンディ(女児向けの代表作)を見ている、女子はみんなマジンガーZ(男児向けの代表作)を見ている
「え?」
「その後には、いわゆる少女漫画ブームも起きていて、男のマニアが少女漫画を読むことも当たり前だったのだ」
「でも、今は当たり前じゃないよね」
「今は、というか1990年代には既にそういう状況は収束していたと見るべきだろう。1980年代に既にそういう傾向は出始めているのかもしれない」
「なぜ男女文化が入り交じった時代があるのかな? なぜ分離したのかな?」
「1970年代、男女文化が入り交じった時代があるのはある意味で当然だ。少女漫画は男の領域をどん欲に取り込だ。実際に、SFを取り込んで百億の昼と千億の昼まで少女漫画にした。それに、そもそもアニメの絶対放送本数が極めて少ない上に、一家にテレビは1台しかないのが標準的だったのだ」
「カラーテレビを家族に占領されたので、モノクロテレビでヤマトを見たって話もあるじゃない」
「あるある。というかそれは自分の体験でもある。カラーテレビへの買い換えはどの家でもあったよくあるイベントだったが、その時点でモノクロテレビはまだ使える状態だった可能性が高いので、そういう意味での2台併存はあり得る。でもモノクロは使わないで済めば使いたくない。色が付かないからね」
「そうか。裏番組が強力でない限り、2台目の出番は無いわけだね」
「基本的に1台のテレビをみんなで見る。居間に置いてあって家族もみんないる。弟がマジンガーZ見てるとお姉ちゃんも見ちゃう。それはよくある光景だった」
「なるほど。ということは、その時代が終わることで男女文化の分かれたと思うべきなのかな?」
「テレビ台数の増加や、ビデオによるタイムシフト、個人宅内の個室の普及など理由はいろいろあるだろう。また、アニメなどでも、男向け女向けの分離が進んだ」
「どんな風に?」
「男向けは女チーム(例:セーラームーン)、女向けは男チーム(例:超者ライディーン)というスタイルで分化していったよ」
「でも、それより前のアニメもみんな男チームじゃない。せいぜい女は紅一点だよ」
「うん。いい指摘だ。でも昔のアニメは、チームに男の子が感情移入できるキャラがいた。たとえば、ガッチャマンのG4号だね。でも、この後の女向け男チームにそういうキャラは入らない。そこが違う。なぜなら、女が感情移入できる女主人公は必要でも、男の子が感情移入できるキャラは要らないからだ」
「なるほど」
「しかし、2010年代の新しいトレンドとしてはこの垣根が壊れ始めているとも思う」
「どうしてだい?」
「たとえば、SPACE BATTLESHIP ヤマトという映画の客層に男女の偏りはない」
「どうして?」
「戦闘アクションを見に来る男もいれば、木村拓哉を見に来る女もいて、同じ暗い部屋に入って一緒に同じ映画を見ているからだ」
「なるほど」
「あるいは、最近流行の『男の娘』というトレンドもジェンダーを越境しつつある」
「『しつつある』とは微妙な表現だね」
「うん。事実として微妙なんだ」
「どのへんが?」
「女にしか見えない外見を整えた男が、女の聖域(たとえば女子校)に入るという部分は、実際には男の願望の範疇であると言える」
「うん。それは入って見たいよね」
「でも、女にしか見えない外見を整えた男が、男性に惚れたとすると。話がひっくり返る」
「そうか。その場合は、男チームを見る視点が違うわけだね」
「そうだ。感情移入できるG4号のようなキャラは要らない。むしろ感情移入できるのは、女が感情移入できる女性主人公になるんだ」
「かなり屈折しているぞ」
「うん、構造は複雑だ」
「ややこしいね」
「だから、『ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜』のような凄く微妙なアニメも出てくる」
「どこが微妙なんだい?」
「一見して、男チームの女向けに見えるが、男の視聴者が入っていける間口があるのだ」
「どのへんが?」
「鉄道とその施設はむしろ男性向けの興味対象であるし、毎回出てくるゲストキャラはみんな可愛い女で、レギュラーにガイドのあかりもいる。イケメン男性でも時代劇マニアがいたり、男でも『そうそう』と入っていける余地がある」
「なるほど」
「この『ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜』が2009年10月から同年12月までで、期間としては隣接しているのだ」
「固定化された枠組みが壊れ始めた予兆だね」
「もちろん、ヤオイという趣味が消えるとは思っていないが、おそらくヤオイ趣味ないしそれに隣接する文化を担う男性も増えていくと思う」
「そんなことが可能なのかな」
「おそらく可能だろう。実際、昔おいらもシュラトとかトルーパーの同人誌アンソロジー本を買って読んだことがあるぞ。ずばり、トルーパーのは面白かったぞ。ちゃんと笑えたし」
「いや、笑いじゃなくて、ヤオイだって」
オマケ §
「実は魔法先生ネギま!という作品も、性差崩壊の予兆を含んでいる」
「どうして?」
「ネギ先生というのは基本的に子供であり、男でも女でもないのだ」
「そうか」
「しかも、魔法で男の大人に変身するケースも、女装させられてキツネギになることもあるのだ」
「なるほど。微妙だね」
「実際に、巻末の読者投稿コーナーなどを見ると年少の女性ファンも多く付いているようだ」
「確かに、男向けの女チームものとも言い切れないね」
「実際、頑張るネギ先生というのは、男が感情移入するようなものではなく、むしろみんなで応援するタイプだ。そうなった場合、応援しているクラスメートのみんなの方がむしろ感情移入する対象になり、むしろ女の方が感情移入しやすくなるという屈折もあるぞ」
「ははは。それは屈折している」
「でも、それは新しいトレンドとしては適切で、あまり男性的な性欲を溢れさせてはいけない作品だったのだ。そのへんを分かっていないマニアも多いみたいだけどね」
「あくまで、男性向け女チームものとして扱いたがるってことだね」
「それが古い時代の常識だからな」
「でも、それが分からないと女性ファンが居るイコール自分たちが女性から理解されたと誤解するわけだね」
「そうだ。そこは誤解だ。男女どちらも入れる場が提供されることと、自分たちが理解されることは全くの別問題だ。むしろここは互いに譲歩し合うことで、相互理解を進めるべき場なのだ」