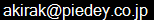「実は、日本沈没は致命的な問題を孕んでいたのではないかと気づいた」
「それはなんだい?」
「それは未来予測と予言を明確に分けられなかったという点だ」
「詳しく説明してくれ」
「日本沈没というという作品は、田所教授が日本は沈没するという衝撃的な未来を予測し、結果として日本から日本人全員が脱出するという話だ」
「未来予測だね」
「そう。でも予言でもある」
「そもそも未来予測と予言はどう違うんだ?」
「未来予測はこのまま行くとどうなるかの予測。前提が変わればいくらでも結果は変わる。それに対して、予言は未来の事象の語り。当たったか外れたかしかない」
「ふむふむ」
「だから、たとえば【このまま放置すると2000年に多くのコンピュータシステムが誤動作して社会が麻痺する】という2000年問題は、未来予測」
「でも、誤動作しなかったよ」
「技術者がみんなで対策したからだ」
「つまり、前提条件が変われば結果も変わるわけだね」
「そう。ところがこれを予言と受け取った人が多くいた。だから、【予言が外れた】と解釈した」
「それは正しくないじゃないか」
「そう。正しくない。しかし、彼らには未来予測と予言を正しく区別できるスキルはなかったのだ」
「それは日本沈没とどう関係するんだ?」
「日本沈没において、日本の沈没は人間が左右できるようなスケールの問題ではないとして描かれている。つまり、前提条件を変えることができない。沈むしかないんだ。だから、未来予測と予言の違いは一切顕在化しない」
「つまり、未来予測と予言の違いを一般人に知らしめる教育的な効果は持たなかったわけだね」
「そう。だから、未だに未来予測と予言の違いが分かっていない人がとても多い」
「なるほど。良いチャンスだったのに惜しかったね」
フィクションと現実の境界が曖昧な人 §
「ついでに言えば、【未来予測と予言の違いが分かっていない人】に隣接する問題として、【フィクションと現実の境界が曖昧な人】という問題がある」
「なぜそれが隣接するんだい?」
「そもそも、【未来予測と予言の違いが分かっていない人】という人は仮定の問題を扱うことができていない。未来は一つであり、未来に対する語りは【当たり】と【外れ】しかない。状況を仮定して、こうならこうなる、という思考を行うことができない。この【仮定ができない、あるいは不得手】という問題は、【フィクションと現実の境界が曖昧】という形でも顕在化すると考えられる」
「【フィクションと現実の境界が曖昧】って具体的にどこなんだ?」
「たとえば、テレビの報道番組などで流れるストーリーのある報道を事実として受け入れてしまう。でも実際に起きた事件に始まって終わる綺麗なストーリーなんてあるわけないよね。あれは後からテレビ局で作った筋書きに映像を当てはめて作っているだけなんだ」
「わあ。そういう人はきっと多いよ」
「だから危ないんだよ。インチキの江戸しぐさが教科書に載って、インチキのパイプ業者の広告が都営地下鉄の車内に載るわけだ」
「ところで、なぜそれが日本沈没と関係するんだ?」
「日本沈没ブームの頃、小松左京先生のところに【自分の土地は大丈夫か】と問い合わせた人がいたという話をとこかで読んだ。典型的な【フィクションと現実の境界が曖昧な人】だろう」
「日本はなんて美しい国なんだろうね!」