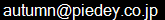「東京国立近代美術館フィルムセンターの展覧会 アニメーションの先駆者 大藤信郎というのを見たんだが」
「うん」
「そこで重大なことに気づいてしまった」
「なに?」
「この展覧会では昔の映画のワンシーンを上映していたんだ」
「どういう内容なの?」
「モノクロのチャンバラ映画なんだろう。いざ戦いが始まる前に、大藤信郎のアニメーションが挿入される。お月様が女性で、恥ずかしそうに顔を隠すんだ」
「なるほど」
「その後で戦いが起こるアクションシーンだ」
「チャンバラということだね」
「で、またアニメーション映像に変わって月がおそるおそるまた見てみると主人公がたった1人で立っていてびっくりする。みんな倒されたんだ」
「うん」
「モノクロだから、おそらく鉄腕アトムや白蛇伝より古そうだ」
「つまりどういうことだい?」
「実は、アニメと実写の境界は初期にあっては曖昧であった、ということだろう」
「初期には、アニメの鉄腕アトムも実写映像の中に出てきたしね」
「つまりさ。押井守がもうアニメと実写の境界がないと言ったところで、実はそれは目新しい状況ではなく回帰でしかなかったわけだ」
「なるほど。回帰か」
「だから、軽井沢シンドロームも、実は映像としては失敗したけど、企画としては思ったほど奇異じゃなかった」
「たがみよしひさ原作の初期OVAの1本だね。本編はアニメだけど、途中で実写の女優のイメージ映像が入る」
「あれが失敗した理由は明白で、軽井沢シンドロームのOVAをわざわざ見る客層は、たがみよしひさ的な独特のキャラを見たかったのだ。あのアクの強い絵柄をね」
「しかし、同じキャラが女優でも出てくるがギャップがありすぎる」
「女優にはたがみよしひさ的なアクは無いからね」
「だから、あとで実写をアニメに差し替えたバージョンが出てくるのは当然なんだ」
「当然か」
「でもさ。実写が否定されるのは、軽井沢シンドロームだからであって、一般論ではないことになる」
「そうか」
「実際、NHK教育のバーチャルシリーズは、実写、アニメ、CGを合成して成功しているし、ファンも多い。彼らは別に実写映像を否定しているわけではない」
「そうか。そういう流れからすると、アニメと実写の境界は最初から曖昧だったんだ」
「うん、そうだ。単純に、それを上手く処理する映像センスが難しかっただけだ」
「技術の問題ではないわけね?」
「技術の問題でもある。つまり、技術の進歩ですりあわせが格段にやりやすくなったのだ」
「なるほど。じゃあ、それにも関わらずなぜアニメは別者という思想が普及したんだろう?」
「制作スタッフが違うとそこで分離してしまうのだろう」
「分離?」
「ほら。戦隊とかでも特撮班が別に存在していて、彼らが仕事をする見せ場はどうしても無くせない。アニメでも、セル画班とCG班が別に存在しているケースがあるようだ。場合によっては別会社ということもある」
「それで分離しちゃうの?」
「バーチャルシリーズでも実写とアニメでスタッフの仲が悪かったという話もあるらしい。それに儲けのことを考えれば、全部自分で引き受けた方がいいに決まっている」
「ああそうか。複数技術の混在はともかく難しいし、本質的に要らない苦労を発生させるから、長続きしないんだ。逆に分離に対する誘惑はある」
「うん。だから、初期と成熟期にしか出現し得ない。その中間の時代には排斥されてしまうんだ」
「いまは成熟期?」
「そうだろう」
「中間の時代でも、マクロス2012とかアニメも実写も含む作品はあるよね」
「でも、音楽アニメだからなあ。一般論としては少し違う」
「マクロスのエンディングも実写入ってるよね」
「でも見てるのはアニメ絵のアルバムなんだよ」
「今だとヒーローマンのエンディングとか、実写入ってるよね」
「不自然さがかなり緩和されて、技術の進歩がよく分かる。確かにアニメと実写の境界はもう曖昧だ」
というわけでヤマトだ §
「で、この話がどこに行くのかという話なのだが、ヤマトだ」
「ヤマトか」
「もろちんだ。もとい、もちろんだ」
「パンツ1枚で艦内一周よりもエッチそうだ」
「パンツ1枚で警官隊の前に立つOOO第1話よりマシだ。って、ちがーう」
「それで?」
「だからさ。ヤマトの実写版というのは、最初に思ったほど企画として浮いていないのではないか、という気がしてきた」
「そうか。西崎さんもおそらく大藤信郎のアニメーションとかを見て前提としている世代だろうからね」
「やればできるのであって、問題はどうするのかだけだ」
「そうか。実写版をやるというのは、ハードルじゃないわけだね」
「やる、できるは最初から分かりきったこと。問題はどうするかだ」
「どうするかの問題は技術の進歩がかなり埋め合わせてくれそうだね」
「実はそういう認識を持つとすれば、権利関係の争いでヤマトの再始動が遅れたのは幸いだったのかもしれない」
「十分な技術は今ならあるってことだね」
「YAMATO 2520の頃にはまだ無かったからね」
「だから、実写の女優がシームレスに不思議な世界に落ちていけるアリス・イン・ワンダーランドが成立する年に、ヤマト実写版も来るというのは意味があるのかもしれない」
「ということは、ヤマト実写版の見所が変わってくるかもしれないね」
「うん。そうだろう。実写でヤマトができるか、ではなく、実写のヤマトをどう描くかに焦点が移っている」
「でもさ。客は付いてこられるのかな?」
「アリス・イン・ワンダーランドを見た客が、年末はトロンとヤマトのどっちを見ようかなと悩むのなら、おそらく問題なく付いてきているのだろう」
「オタクは?」
「知らん。たぶんヤマトの客じゃないから関係ない」
「アニメに詳しければ詳しいほど境界線があるという常識が邪魔になって迷走しそうだとは思わない?」
「それ以前に映画館に来ないだろう。萌え映画以外はね」
余談 §
「アリス・イン・ワンダーランドは2Dの方が面白かったという意見もあるようだけど」
「おいらは3Dで見た。2Dでは見てない。でも2Dの方が面白いとは思えないな」
「でも、そういう感想があるのはなぜだと思う?」
「詳しいことは知らないが慣れの問題があるのかもしれない」
「慣れ?」
「3Dメガネにはいくつかの方式があって重さ等の差もあるらしい。それらを掛けることに慣れているのか、という問題がまずある」
「慣れていないと、メガネが気になって映画に集中できないものね」
「こちらは遊☆戯☆王の時点でメガネの初体験を済ませて、同じ劇場だから同じメガネを毎回使って、アリス・イン・ワンダーランドの時は既に慣れた状態で見ていたから、別にメガネは気になってない。でも初体験の時は気になったよ」
「そこに個人差がありそうだね」
「大いにありそうだ」
「じゃあ、各家庭に3Dテレビって普及すると思う?」
「どこまで普及するかは知らないが、普及しても不思議じゃないと思う」
「なぜ?」
「3Dコンテンツの蓄積が増えてきているからだ。劇場では3Dで見たあの映画が自宅で2Dだと悲しいからな」
「多チャンネル化が進めば2D3D同時放送も簡単だね」
「自宅でいつも使っていればメガネにも慣れるだろう」
「メガネがないのが本当は理想だけどね」
「他には3D酔いという問題は確かにあるけど、あれも慣れの問題だと思う」
「慣れかね?」
「うん。慣れだ。ACE COMBATでも自機を全方位振り回すとすぐ機位を失って落ちてしまうが、実は慣れと言うことが良く分かった。振り回さず、常に機位を把握しながら飛んでいたら、いつの間にか振り回しても平気になったぞ」