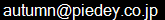「以下は某サイトで見た文章だ」
昨日のラノベの話ですが、「意外と作家買いがされない」というのは数字上の事実で、ラノベ出版社の悩みの種だそうです。
「へぇ。ラノベなんて買わないし読まないから知らなかったよ」
「しかし、ラノベの客層がそのままオタク層であり、アニメを見ているとすると、これで以下の謎が解ける」
- ガオガイガーを喜んで見るオタクが、同じ米たにヨシトモ監督の熱い作品であるザ・ドラえもんズはまるで見ようとしない
「その話題は前にも出たね」
「つまりさ。声優は分かるけど、監督は分からないんだよ。言葉の上で監督という役職の人がいると分かるけど、彼らは追いかけない」
「でも、声優は追いかけるんだよね」
「そうだ。しょせんは、アニメファンの皮をかぶった声優ファンでしかない」
問題はアニメ §
「で、その話がどうしたの?」
「ラノベやコミックは、属人性が高い。従って、男おいどんが面白かったからワダチも読んでみるという流れは比較的起きやすい。ワダチを読んでSFものもいけると分かると次はマシンナーズシティを読んでみるかも知れない。更にジャンルを超えて行けそうだと思えば、ガンフロンティアや戦場まんがシリーズまで手を出すかも知れない」
「うん。そうだね」
「だから、ヤマトの小説を書いた若桜木虔だから、アンドロイドジュディも読んでみようか、というのも自然な流れだ。あるいは、ヤマトの小説を書いた石津嵐だから、宇宙潜行艇ゼロも読んでみようかと思うのも自然な成り行きだ」
「それは当たり前だね。君がオタクではなく、作家買いを意識しているなら」
「ではそこで問おう」
「うん」
「アニメの世界とは、実は集団作業だ。個性を主張できる役職は多くないのだが、それでも複数ある。シナリオライターが自分の世界を展開しつつ、作画監督が別の世界を展開していくこともある」
「うん」
「だから、アニメは異なる個性、異なる考え方の複数人が共通の目標に向かって協業した成果物といえる」
「それで?」
「そのような世界で、作家買いはあり得るのだろうか?」
「なんか急に難しくなってきたな」
「小説の世界で作家買いの有無を論じることは意味がある。でもアニメの世界では、どこまで意味があるのだろうか」
ヤマトってのは §
「だからさ。逆に1つの価値観に従い人には従わないという生き方もでてくるわけだ。それが作家買いしない、という方向性で出てくるのかもしれない」
「ああ、そうか。だからヤマトは実は特定個人の才能だけに依存しないってことか」
「まるで違う内容のヤマトの小説がいろいろあるけど、その状況を容認できるのは属人的な価値観ではないから、なのだね。たぶん」
「そうか。だから、松本先生のいるヤマトも、いないヤマトもOKなんだ」
「問題はそこで多様性を認めるか認めないかで、1つのヤマトという価値を解釈する方法が複数あることを容認するか否かだ」
「そこが問題か」
「だから、この問題は以下の対立のように思えるがそうではない」
「つまり、以下のようになるわけだね」
- 作者にファンがつく
- 表現にファンがつく
- 価値観にファンがつく
「なるほど。表現にファンがつくってのは、アニメであっても原作と違うことは容認しないとか、アニメーターの個性で絵が変わることは容認しないっていう狭い解釈だね」
「うん。それに対して、価値観にファンがつくというのは、いろいろなやり方を許容するもっと幅の広い受容なんだ」
「それは重要なことかい?」
「そうだ。復活編はまだしもヤマト関係者が中核を固めたから継承性があるが、実写版はもう継承性もない。しかも、表現も別物になる。その状態で実写版をヤマトとして受容するには何が必要となるのか。それは間もなく問われるわけだ」
「じゃあ、未来予測として12月になって実写版が公開されると何が起こると思う?」
「こんなのヤマトじゃないという大合唱、だろうな」
「で、君はどうするの?」
「別にどうもしない。ケツの穴が小さい奴らだな、と思うだけだ」
「そりゃまた厳しい言い方だね」
「だってそうだろう? ヤマトってのは戦艦大和にでかいケツの穴を開けた存在なんだ。波動エンジン噴射口っていうね」
「おいおい」
「つまり。ヤマト・イコール・ケツの穴が大きい」
「そんな、ゴーダム・イコール・ゴワッパー5みたいに言わないでくれよ」
「ゆくぞヤマト。発進だ。みんなの幸せ守るため、ガミラスボーグを踏みつぶし、超巨大戦艦に体当たり♪」
「洒落にならねえ」