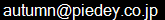「シアタス調布が割り引きの日なので何か見ようかと思ったら未来のミライを上映していたのでそれを選んだ」
「それで?」
「適当に時間を選んで行ったら何と3000円でな。絶句した。特別なスクリーンだったらしい」
「えー」
「しかし、その前の回がまだ売っていたので、上映開始ギリギリだと思って即座に切り換えてそれを購入。スクリーンにダッシュした(トイレ経由だけど)」
「間に合った?」
「予告は全て終わっていたが、映画本編にはギリギリ間に合った」
「それは良かったね」
「さて、実際に見た感想だが、要するに【前にヒットしたものと同じようなものでないと企画が通らない環境と、違うことをやりたい、やらねばならない細田監督のバトル】が垣間見えた気がした。気がしただけだけど」
「どんなバトルだよ」
「宣伝やタイトルは時をかける少女的だが中身は全くの別物だったということさ」
「実際の内容はなんだい?」
「長男もの……だな。妹が生まれて親の愛を失って釈然としない子供の映画。タイムトラベル要素は基本的に無い。ミライちゃんは未来で待っていない。過去や未来は見えてしまうだけで、基本的に過去や未来を変える話にはならない。変わるのは現在の主人公。一人っ子から兄貴になる」
「ミライちゃんは?」
「ストーリーの軸ではあるが、主人公ではない。出てこない展開も多い」
「他に何か言いたいことはあるかい?」
「うん。ちょっと辛辣なことを言えば、この映画は失敗しなかったシンカリオン」
「は?」
「鉄道、特に新幹線がサブテーマであって、最終的に黒い新幹線に乗るか乗らないかが問題になる」
「黒い新幹線って、どこのシンカリオンですか」
「だからね。ドライブヘッドに比べて食い足りないところが多かったシンカリオンのどこが不味かったのかを身を持って示してしまったのがこの未来のミライという映画ではないか」
「たとえば?」
「歴然として違うのが、主人公の鉄道に対するスタンスで、シンカリオンの主人公は知識を羅列しているだけでなぜ好きなのか、どう好きなのかがまるで伝わってこない。ただの痛い人にしか見えない。マニアには見えない。それに対して、未来のミライのくんちゃんからは【好き】という感情が伝わってくる」
「マニアに見えるの?」
「見えないよ」
「じゃあ何に見えるんだよ」
「年齢相応の子供に見えるよ」
「そこがシンカリオンで食い足りなかった要素?」
「そう。キャラクターが年齢相応の子供に見えない。小さな大人に見えてしまう。まあそういう事例はアニメに多いから、あまりとやかくは言わないけどね。でも、こうまで露骨に比較できてしまうとねえ。うーん、とうなってしまった」
「じゃあ、もうちょっと君の個人的な感想を言ってくれよ」
「東京駅の描写は良かったね。ロボット駅員がいて広々とした架空の東京駅内部」
「他には?」
「序盤でくんちゃんが着ているパーカーが中央線201系というのは良かった。たぶん、細田監督って一種の鉄道マニアだよ」
些細な余談 §
「くんちゃんの家が横浜にあるのは、おそらく東京駅に行くという展開と、横須賀の軍港の横をバイクで通過するという2つの条件を付けると必然的に導き出されるロケーションだろうね」
「なるほど」
「それからくんちゃんに姓の設定がなく、父母に至っては名前の設定すらないのは見ている観客ごと【家族の名前を言うことができない】という感覚を味わうためだと思う。名前の設定があるくんちゃんの家族はミライちゃんだけなので、必然的にくんちゃんはミライちゃんの名前を思い出さねばならない。そして、未来のミライちゃんと既に会っているがゆえに、未来のミライちゃんに助けられるしかない」
「いろいろと構成が良く出来ているわけだね」
「設定は増やせば良いというものではない。キャラクターにはどんどん名前を設定すれば良いというものではない。そういうことだろう」