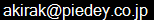読みやすく、文章量も多くないので、サクッと読み終わりました。
読み始めたら最後まで読まされてしまった、という意味では面白い本と言えるかもしれません。
ただ、内容に関して賛成するかというと、ちょっと難しいですね。
よく調べているとは思いますが、調査不足、追求不足、安易な結論に飛びついてしまう心の弱さがあるように感じられます。斎藤環さんであるとか、大塚英志さんであるとか、そういうレベルの人達の書いた文章と比較して、まだまだ精進不足という感じを受けます。
とはいえ、建築という視点から秋葉原を見るのは興味深い新しいものだと感じました。一応、古い建築物ミーハーで、好きなものは看板建築とか口走ってみたりする立場なので。秋葉原の建築物が、窓のない形に進んでいるという指摘は興味深いところがあると思います。もっとも、窓を無くすことは、精神的な内向性というよりは、モニタに直射日光が入ると困るからに過ぎないのではないか、という気がしないでもありませんが。
さて、帯には『いつの間にか街全体が巨大な「個室」になているのを知っていますか?』と書かれているのは悪くないと思います。「個室」というのは良い表現で、まさに、私が既に秋葉原を素通りして両国に行ってしまう理由を(極めて不確かで曖昧で間接的ながら)上手く表現しているような印象を受けます。
つまり、私自身、最近では秋葉原にはさっぱり魅力を感じず、パソコン関係の買い物といえば新宿ばかり、なじみのパソコンショップは秋葉原に近いとはいえ秋葉原にはないQualestだったりして、そのことに何の問題も感じていなかったりする理由として、けっこう妥当かなと。そんな風に感じたわけです。1990年代初期の、まだ秋葉原に行く価値を感じていた時代というのは、秋葉原は先鋭的な文化の発信地としての側面を持っていたと思います。パソコンにおけるIBM互換機文化は、秋葉原を経由して受容するしかなかったものです。他の地域にいくらパソコンショップがあれど、それはマンネリ化した国産パソコンしか扱っていない店ばかりだったのです。しかし、今の秋葉原に、それに匹敵する先鋭性は感じられません。先鋭性がないと言うことを表現するために、小さく閉じこもってしまうイメージをかき立てる「個室」は似合っているように感じます。
とはいえ、全般的に評価するなら、この本は一般の読者にはお勧めではありません。