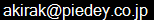読みながら非常に興味深い本だと思いました。
なぜなら、1980年代とは自分が生きた時代であり、実は本書に出てくる固有名詞の多くとは驚くほど関わりがあったからです。
つまり、何について語っているのか、それが分かるということです。
それにも関わらず、それに触れた立場の決定的な相違は、私が見知ったものとは違う別の姿を描き出します。
つまり私の体験という線と、大塚英志さんの体験という線は、同じ1980年代という時代を走りつつも平行していなかったと言うことです。
そして、自分の体験に加えて、他人の体験を参照することによって、それを成立している2本の線の中間領域が把握可能な世界として広がります。
1本の線が2本に増えることによって、それまで線でしかなかったものが面に広がる面白さは、過去にも経験したことではありますが、非常にエキサイティングで世界がパッと広がる思いがします。
と思ったのは実は間違いだった §
途中まで読みつつ思っていた、そのような感想は実は間違いでした。
この本は、そのようなつまらない本では全くなかった!
本書本文を締める以下の文章が明瞭にそれを意識させてくれました。ちょっと長いですが引用します。
p426より
主体たれ、というこの国の戦後史が禁じた自己実現への欲望を最後まで抑止しようとした「エヴァンゲリオン」の直後に起きた神戸連続児童殺傷事件は、主体をめぐる欲望にとうとう抗い切れずそれを解き放った点で戦後のサブカルチャー史の終着点にあるようにぼくには思える。そして少年のような若者が多数派であるとすれば、消費財としてのサブカルチャーは否応なく主体をめぐる欲望に輪郭を与え、言葉を与える物語を紡ぐ必要に迫られる。神戸の事件と前後して急速に「公」や「国家」といった主体の構築に向かっていた小林よしのりの『ゴーマニズム宣言』はその意味ではサブカルチャーとして鋭敏な選択だったと言える。そこで語られる「公」や「国家」が「酒鬼薔薇聖斗」の代替物として相応の訴求力を持っていることは確かだし、少年の透明な主体はぼくが透明なナショナリズムと感じるものの一つの前史であったと今になれば思うことは可能だ。
つまり、人間が「主体」を求めているが、それが必ずしも満たされていないと言うことです。そして、それを満たし得ているものが、『ゴーマニズム宣言』の 「公」や「国家」であるとすれば、現在の日本の居心地の悪さの理由も分かるというものです。いかに、『ゴーマニズム宣言』が陳腐で粗悪で、出来が悪いとしても(本当にそうかは読んでいないので分かりませんが)、それがニーズを満たすのであれば支持されるのは当然。むしろ、もっと他により好ましい別の何かが存在しないことが問題と言えます。そして、大塚英志さんは、サブカルチャーにそれを生み出すことを求めているように読めます。
(より具体的に言えば、このやや手前に書かれた通過儀礼について考えることが適切でしょうか?)
つまり、この本は過去の話を書いているかのように見えながら、最終的に、現在という視点から我々の未来を見ています。これは極めてエキサイティングですね。面白いです。そして、我々が住んでいるこの社会をいかに維持していくかという切実な問題に直接関わります。まだ数十年はこの社会の中で生きていくであろう私からすれば、全く利己的な動機において、社会が健全性を維持することは必須の要求でもあります。
過去を再興するようなありえない夢想ではなく、今目の前にある現実に対して、いかなる生きる主体を示しうるかは、考える価値のあるテーマであるような気がしました。
成熟は免除されない §
非常に良かったのは以下の1文です。
p354より
ただ、「男」と「女」や「大人」という枠組みが喪失したことと、人が何かに向けて「成熟」から免除されたことは必ずしも同じことではないように思えた。
これは実感として良く分かります。
インターネットを見ていると、書き手の成熟の度合いの差というものが、露骨に見えます。インターネット上では誰もが対等であり、あらゆる人間の差違は意味を持たないはずです。しかし、それは単なるシステムとしての公平性の保証に過ぎず、そのシステムを使う人間の成熟度合いは、露骨なまでに明瞭に見えてしまいます。
そして、成熟が不十分な者は、その明瞭な差を見いだせないために、あるいはそれを本能的に察してしまうために、対等であろうと振る舞います。その振る舞いが、インターネットを不快なゴミの山へと急速に堕していく原動力となっているように感じられます。
ですから、やはり彼らには「成熟」が必要であると感じます。けして、システムの公平性は、人間としての、あるいは別の何らかの意味での「成熟」を免除してはいません。
エヴァンゲリオン再評価 §
非常によく誤解されますが、エヴァンゲリオンという作品は全く評価していません。好きでもありません。これが、いかに底の浅い作品であるかは、最初から痛烈に感じていたし、そのことは庵野監督の「衒学である」という表明によって裏付けられています。
ですから、タダで見られるTVシリーズならともかくとして、金を払って劇場まで足を運んではいません。つまり、劇場版は見ていません。おそらく、金を払う価値はないだろうと思っていました。
しかし、本書で大塚英志氏が評価するとした劇場版のラストは、興味を抱かせるに十分なものでした。機会があれば見てみたいと思いましたが、はたして機会があるか……。いずれにせよ、いかに名作であろうと古い作品よりも、現在進行形で作られるまだ見ぬ新作に時間を使うのが染みついた習性です。