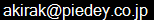既刊全巻読み直しは、ついに超が未来に帰るところまで読み進みました。
さて、読み直しながら思ったことがあります。
ネギま!という作品には、あるいは赤松健という作家には、「常に中心を離れ境界を目指す」という作風があるのではないか?
いくつか具体例を出します。
具体例 §
唐突に普通の女の子の普通の恋愛話に飛ぶ §
学園祭編で非現実的なバトル大会が繰り返された直後、亜子の普通の恋愛話に唐突に進みます。魔法バトルコミックとしての非凡な盛り上がりを的確に描ききったにも関わらず、確立されたその世界から最も遠い「境界領域」とも言うべき普通の恋愛話に進みます。
いきなり舞台が飛ぶ §
いきなり日本で先生をやれと東洋に飛ばされたり、学園祭編で1週間後に飛ばされたり、魔法世界編でメガロメセンブリアからいきなり辺境に飛ばされたり、本来期待された中心的な場所から、境界的な場所に飛ばされます。特に重要なポイントであればあるほど境界的な場所に飛ばされます。
正義と悪の混濁 §
明瞭な「悪」が出現することは多くありません。超の行為は単純な正義でも悪でもなく、それを止めるためのネギは自ら「悪を行うことから逃れられない」と自己規定せずして戦うことができません。あるべき理想の秩序が存在する中心的な世界ではなく、価値観が混濁する境界的世界が描かれています。
学園祭編ラストの超の居場所 §
飛行船の上というのは、まさに学園祭会場という地域概念の境界部分です。
類型としての「境界を目指し続けるタイプ」 §
世間が規定する当たり前の世界、あるいは作者本人が作り出す確固たる世界から常に逸脱して境界を目指す……というタイプは1つの人間の類型といえます。
安定した世界を望むがゆえに中心を目指すタイプと対極といえます。
ちなみに、どちらのタイプが正しいであるとか、どちらがより優れているという話ではありません。あくまで、個人の性格の傾向の話であって、個性の違いです。
そのように考えると、アニメ監督の宮崎駿や押井守も「境界を目指し続けるタイプ」だろうということが容易に推測できます。
裏切り者となるタイプ §
「境界を目指し続けるタイプ」の典型的な特徴は、ある程度以上の実績を積むと以下のような批判に晒されることです。
- 昔は良かった
- 裏切り者
- 変な世界に行ってしまった
- 本当は良い作品を作れるはずなのに
- 本当にやりたいことをやっていない
これらは、「中心を目指して安住するタイプ」の立場から発せられ、他者も同じタイプであるという暗黙の前提から導き出されると考えることができます。つまり、「素晴らしい中心の作り手」であるからこそ、「中心の担い手であり続けることが目標であるはずだ」と考えます。そのような当然のあり方に沿って行動しない者達は、必然的に「裏切り者」となります。
たとえば、宮崎駿がどれほど自分のやりたいことをストレートに出して「千と千尋の神隠し」や「ハウルの動く城」を作ったとしても、常に昔の作品は良かった主張する者達が出てきます。これは、常に今と昔の対比として出現する構造であるのが特徴です。たとえば、天空の城ラピュタが公開された頃は「コナンやナウシカの時代は良かったのに」と言われていたにも関わらず、最近では「ラピュタの頃は良かった」と言われるような矛盾した構造を持ちます。つまり、このような構造において、特定の作品の善し悪しは問題ではなく、既に中心として受け入れられた作品は良く、まだ受け入れられていない作品は悪いという構造があることを意味します。
裏切り者が一般性を獲得する矛盾 §
本来あるべき秩序としての「中心」からの逸脱を指向しているにも関わらず、「境界を目指し続けるタイプ」は逆説的に不特定多数の一般大衆の支持を得やすい特徴が見て取れます。
具体的な事例としては、オタク層から支持されない宮崎駿が一般大衆層から厚い支持を得ていることがあげられます。また、ネギま!巻末の読者投稿イラストを見ると、明らかにいわゆるオタク層とは違う厚い支持層が存在することが見て取れます。
「カオスの縁」 §
「境界を目指し続けるタイプ」という表現は、複雑系における「カオスの縁」という言葉を連想させます。
100パーセントいい加減に書くと、複雑系において世界は「秩序」「混沌(カオス)」に分けられ、その中間に「カオスの縁」が存在します。「秩序」とは変化のない死んだ世界であり、「混沌(カオス)」は何も生み出すことができない無秩序な世界です。新しい何かを生み出す機能性は、「カオスの縁」にしかなく、これを創発と呼びます。
つまり、裏切り者=「境界を目指し続けるタイプ」とは、「創発」を引き起こす者であるという仮定を置くことができます。
「創発」がもたらす価値 §
世の中は常に動いていて、実際に生きている人も変化していきます。それゆえに、確立された「中心」はそのままではニーズを満たせなくなり、支持を失います。
そこで変化したニーズを満たすためには、新しい何かが必要であり、そのために「創発」という作業が不可欠になります。その結果、「創発」を行う者達は、一般大衆から支持を得る可能性がより高いと考えられます。
これに対して、いわゆるオタクに代表されるようなマニア層は、確固たる中心を持った存在であり、「創発」よりも「中心の再生産」を求めるのかもしれません。
このように考えると、なぜ中心から離れて行こうとする裏切り者が逆に一般性を獲得してしまうのか、理由が分かるような気がします。
「感動」と「満足」はどう違うのか §
「感動」は予測もできなかった素晴らしいものに出会うこと。
「満足」は予測した通りの全てが満たされることだと規定してみましょう。
とすれば、個人的に予測できるか否かの問題を横に置いて一般論で語るなら、「感動」を生み出すためには、「創発」が不可欠となります。
つまり、「境界を目指し続けるタイプ」は「感動」を生み出す担い手と位置づけられます。
つまり §
「境界を目指し続けるタイプ」に対して昔に戻れと要求することは以下の2つの理由から誤っています。
- 自分の性格にとって自然なことが、他人の性格でも自然とは限らない。それを押し付けることは相手に苦痛を強いるかもしれない
- 「満足」は高まっても、「感動」は遠のく
感想 §
こういう文章を書いたのは、自分も典型的な「境界を目指し続けるタイプ」だな、と思うからです。
しかし、発端は「なぜ学園祭編に、あまりに唐突な感じのある亜子のエピソードがあるのだろうか」と考え始めたことです。
その後で、宇宙の果てで宇宙の危機が起こった直後に地球の危機があって戻ってくるペリー・ローダンのストーリー構造という話題を思い出して、考えを進めました。
ちなみに、作品構造的な観点からネギま!とペリー・ローダン(宇宙英雄ローダン)を比較してみる価値があるような気がします。