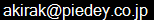「オタクの常識である「データベース」解釈が決定的に古く誤っていることを明示的に示すネギまの秀逸性!!」で、ネギま!はデータベース型ではなく外部参照型の作品ということを示唆しました。しかし、この示唆は実はあまり意味がありません。通常、作品から外部参照を全て除去することはまず不可能であり、両者の境界は曖昧だからです。
しかし、それとは別にネギま!という作品が一般の外部参照型作品と異なる特徴があります。それは、ネギま!においてはしばしば「外部参照が多重化される」という特徴です。
多重外部参照の例 §
ネギま!では、日本語で書かれた呪文にカタカナでラテン語のルビが付きます。
これは、単純な翻訳や、読みを付加したルビというだけではなく、日本語は日本語単体で呪文や詩としての形式を持ち、同時にラテン語はラテン語の独立した呪文を形成します。これは、構造が二重化されています。
しかし、単なる言葉の二重化を超えて、言葉の由来まで二重化されているケースも見られます。
たとえば、朝倉のアーティファクトである『渡鴉の人見 (オクルス・コルウィヌス)』は、22巻の巻末を読むとカタカナ部分は北欧神話を、日本語部分は古事記を参照して由来が説明されています。これはもう、「凝りすぎ」としか言いようがありません。しかし、このような表現がもたらす効果は絶大です。ネギま!世界は、北欧神話と古事記の神話の世界を包含しているのです。いや、単に包含しているのではなく、それらに対して一貫する解釈を提示することで、それらの神話の中間にあるはずの諸々すら描く力があることを示しているのです。
別の例 §
刹那のアーティファクト『匕首・十六串呂 (シーカ・シシクシロ)』は、カタカナ語の言語が一貫していないという面白い特徴を持ちます。つまり、「シシクシロ」は「十六串呂」の読みである(と思う)のに対して、「シーカ」は「匕首」の読みではない(と思う)のです。おそらく、シーカはラテン語でしょう。しかし、この言葉に途中で言語が変わる唐突感はありません。なぜかといえば、「シシクシロ」という単語そのものが、ラテン語に馴染む語感を持っている(ような気がする)からです。だから、固有名詞として「シーカ・シシクシロ」なる言葉が作中に用いられても、それはそれで作品に馴染んでしまいます。
にも関わらず、この言葉を分解すると、全く異質な出自が浮かび上がってくるわけです。そのような意味で、『匕首・十六串呂 (シーカ・シシクシロ)』も多重化された外部参照を抱えていると言えます。
感想 §
そうそう。これなんだよね。
問題は、データベースはダメだとか、外部参照があれば良いといったレベルの話ではないのですよね。
ネギま!が多重外部参照型であることは、それ事態良いことでも悪いことでもありません。
真の問題はその作品は面白いのか、いつまでも楽しめる奥行きがあるのか、といった点にあるわけです。
ここで重要なのは、ネギま!が多重外部参照型であることではなく、多重外部参照という技を用いることで、ネギま!が飽きさせない面白さを作中に織り込んでいる点にあります。