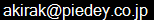トーノZEROさんが蒼穹のファフナーというアニメ作品の感想としてもしかしたら2ちゃんねる的匿名掲示板世界の他に、進むべき道があることを示したかもしれない傑作エピソード!?というものを書いています。
ここで示唆された「個のないすべて1つである世界に戻っていくのか、それとも先に進むのか」という問題提起は、トーノZEROさんによって、「個のない世界→匿名掲示板文化」に結び付けられています。
これは昔の疑問への解答になる? §
実は、これはずっと昔に私がtestml3というメーリングリストに書いたことの解答になりうる内容である可能性に気付きました。
以下に要点を引用します。
今月の月刊ASCIIの121ページで、まつらさんのkakikomi.comが紹介されていま
す。そこまでは良いのですが。
宣言文を(中略)をたっぷり入れながら引用したあとで。
「気持ちはわからないでもない。だが、他人への過剰な気遣いとフェイスマーク
があふれかえり、本質的な議論がなかなか始まらなかった日本独特のパソ通文化
が、それほど素晴らしいのだろか?」
と書いてあります。
うーむ^^;
この筆者のいう「日本独自のパソ通文化」って、具体的にどこのことなんでし
ょ?
少なくとも、私が見てきた、NIFTY, PC-VAN, mix, その他10あまりの草の根ホ
ストのどれも上記の条件に当てはまらないですけどねぇ^^;
気遣いを知らない連中はいつまでも根絶されないし、あふれかえるほどフェイ
スマークが使われていれば誤解による喧嘩はもっと少なかっただろうし、いきな
り本質的な議論を吹っ掛ける礼儀知らずは多いし。
もしかして、会員が集まらないで、すぐ消えて無くなったどっかのパソ通ホス
トでは、彼が言うような文化があったんでしょうかね?
でも、そんなもんを、パソ通全般に一般化して書かないで欲しいな。
この文章を要約すると、以下のようなことになります。
- 月刊ASCIIに記載された文章である
- そこではパソコン通信の問題点が列挙されている
- そして、問題の多いパソコン通信が素晴らしいのかという疑問が提示されている
- しかし、私にはそれに該当する「パソコン通信」に心当たりがない
- 私の知っている「パソコン通信」ではないとすれば、それはどこの「パソコン通信」だろうか?
『それはどこの「パソコン通信」だろうか?』という問いに対する答は、最近になって手に入れたような気がします。つまり、それは私が見ていたパソコン通信と同一のものであった、ということです。それはどういう意味かということを以下に説明します。
パソコン通信の参加メンバー的構造 §
パソコン通信というのは、誰でも参加できるコミュニケーションシステムです。その点で、インターネット上の匿名掲示板システムと同質のものと言えます。
両者の相違は、主に個人識別を行うか否かにあるかと解釈できます。(以前に書いた文章を参考まで、2ちゃんねる型匿名掲示板に構造的問題点はあるか?)。他にもいろいろな相違がありますが、時代的、技術的な背景がバックにあるもので、本質的な相違とは言い難いという印象を持ちます。
さて、パソコン通信では、読むだけの人をROM(Read Only Member)と言います。それに対して、自らメッセージを書き込む人をRAM(何の略であるかは不詳)と呼びます。
パソコン通信の世界は、ROMとRAMから構成されます。通常、ROMの存在はあまり明確に見えていません。しかし、ROMもメンバーである、ROMは大切にしなければならないという意見もあり、私もそれを肯定していました。たとえば、有料の大規模システムなどでは、多数のROMが存在すればこそシステムが維持でき、RAMは書き込む場所を得られるという側面があったわけです。また、パソコン通信では、RAMになることが究極の目的ではない、という考え方があったことも付記しておく価値があるでしょう。ROMはROMという1つの楽しみ方であって、RAMになることが常に正しい訳ではありません。むしろ、RAMをやれるのは特異な少数派であって、ROMであることの方が普通であるとすら解釈できます。当然のこととして、ROMとRAMに人数比率は圧倒的ROMが多いケースが多数派だったように思います。少数のRAMが発言して、それを多数のROMが見ているというスタイルが、1つの典型的なパソコン通信の構造ではないかと思います。
見落としていたものは何か §
ここまでの話の中で、見通されていたものが1つあります。
それは、ROMでもRAMでもない人達です。
つまり、ROMに徹することが自分の楽しみであると割り切ることができず、発言を望みながらRAMになれなかった人達です。
当時、RAMをやっている立場では意識していませんでしたが、ROMから見ればRAMとは小さな舞台に立つ小ヒーローです。それに憧れ、それになりたいという願望を持つことは、けしておかしいことではないと思います。しかし、それを行うハードルは非常に高いと言えます。守るべきマナーは多いし、うかつなことを書けば長老格のうるさ型のベテランRAMに罵倒されかねません。更に、あえて書くに値する話題を誰もが持ち合わせているかといえば、持っていない人の方が大多数でしょう。実際には、そんな価値ある話題は必要なく、たとえば「私、ナウシカの大ファンです!」と書くだけでPC-VAN 宮崎駿ネットワーカーFCのRAMの仲間に入ることは問題なく可能でした。しかし、高度な話題が飛び交っている中に、いきなりミーハーな話題を書くのも勇気のいることでしょう。そのハードルを超えられない人も、少数派ではなかった可能性があります。
では、これらのハードルを超えられなかった人々がいるとして、彼らの立場から見てパソコン通信がどう見えるのかと考えてみると。既に引用した以下の文章のように受け止めたとしても何ら不思議ではありません。
「気持ちはわからないでもない。だが、他人への過剰な気遣いとフェイスマーク
があふれかえり、本質的な議論がなかなか始まらなかった日本独特のパソ通文化
が、それほど素晴らしいのだろか?」
つまり、人と人とが付き合う以上、当然取るべき気遣いが「他人への過剰な気遣い」と受け取られ、多くの誤解によるトラブルの痛い経験から誤解を避けるために使われるようになったフェイスマークは「あふれかえっている」と受け取られ、実はさほど高尚ではない雑談的なコミュニティを高尚であると思い込み、「本質的な議論がなかなか始まら」いと受け取られた、という可能性が考えられます。
という話が正しければ、私の疑問『それはどこの「パソコン通信」だろうか?』という問いに対する答は、自分も知っているパソコン通信であった、という結論になります。
RAMになれなかった人達の行き先はどこか §
では、RAMになれなかった人達はどこに向かったのでしょうか。
パソコン通信に否定的な印象を持った彼らは、おそらくは新天地であるインターネットに向かったのでしょう。
そこで彼らが構築する新しい世界は、必然的にパソコン通信とは異なるものになります。(もちろん、もともとインターネット上にあった実名のnewsの世界とも異なります)
具体的に、どこがどう異なるのでしょうか。
RAMになれなかった、ということはパソコン通信が要求したハードルが高すぎた、ということを意味します。そのハードルは、上記の文章から「他人への過剰な気遣い」「フェイスマーク」「本質的な議論がなかなか始まらない」といった問題であると考えられます。これらのハードルを下げることが、彼らにとっては必須の要件となります。具体的には、「気遣い不用」「フェイスマークのような感情表現記号を使う必要がない」「雑談抜きで何でも本題を書ける」という条件が課せられます。
このような条件を満たすためには、必然的に「個人」という要素が後退します。「気遣い不用」とは気遣う対象の「個人」を意識しないことを意味します。「フェイスマークのような感情表現記号を使う必要がない」とは感情の持つ「個人」がそこにいるという意識を希薄化します。「雑談抜きで何でも本題を書ける」とは「私の考え」「私の気持ち」といった「個人」に属するもの抜きで、ただ事実だけがそこにあるという考えにつながります。
その路線を突き詰めていくと、最終的に完全な匿名の世界が生まれます。そこでは、個人というものは存在せず、誰の書き込みも全て「名無しさん」という存在しない虚構の書き手の書き込みと化します。これは、「蒼穹のファフナー」でいうところの「全てが1つであり個人の識別が存在しない」フェストゥムという存在と類似の性質を持つと考えても良いだろうと思います。
なぜ彼らは気付くことができないのか §
匿名掲示板システムが持つ構造的な問題は明らかです。これは上手く機能しません。
そんなものは誰が見ても分かるだろう、というぐらい当然のことです。
しかし、それを利用する当事者の多くは、そのような問題に極めて無自覚的です。
その理由はここまでの話から明らかになります。
ここで問題にされている匿名掲示板システムの問題に対する答は、ある程度、パソコン通信の時代に既に出ています。パソコン通信のシステムには、それがある程度含まれていたと考えて良いと思います。
しかし、そのような「マシなシステム」に乗ることができなかった人達から見れば、それは有効な解決策ではないことが自明の前提となります。自分たちが乗れないのでは、無いのと同じです。そして、「彼らが乗れる」という特徴と、ここでいう「問題点」は表裏一体の関係にあり、不可分です。その結果、「自明の前提」が「問題点」を隠蔽し、それは意識に届くことが困難となります。
もう1つ、当事者が気付きにくくなる理由が考えられます。それは人数です。既に述べた通り、RAMとROMの人数比率は、圧倒的にROMが多いと考えられます。そのROMの一部が「RAMになれなかった者達」だとしても、RAMの人数を圧倒的に上回るでしょう。つまり、彼らは常に多数派であり、多数派の中で安心し、自分が立つ基盤に疑問を差し挟む必要などは感じられない可能性があり得ます。
もっとも、多数派といっても、社会全体から見れば少数派に過ぎません。しかし、大規模匿名掲示板に常駐していると、圧倒的に多くの情報に飽和して、どちらがより大きいかという感覚が麻痺する状況はあり得そうです。
名前のない世界は「戻る場所」であって「進む場所」ではない、という指摘 §
「蒼穹のファフナー」では、個人の識別が無く、全てが1つであり、会話が存在しない世界を「戻る場所」と表現しています。それに対して、人間が会話を行う世界を「進む場所」として示しています。
ここで、匿名掲示板の利用者も人間であって、匿名掲示板で交わす言葉も「会話」ではないか、と思う人がいるでしょう。しかし、そうではありません。識別できない相手に放たれる言葉は会話にはなりません。
さて、ここで特に注目したいのは、個人の識別のない世界を「戻る場所」と表現していることです。
原初、誰もが名前を持たず、自分と他人を区別していませんでした。人間の精神的な成長にも、他人は自分ではないと気付く段階があるといいます。それを考えれば、このような場所を「戻る」と表現するのはなかなか正しいのかもしれません。
とまあ、そういうことに気付かされたので、こういう文章を書いてみました。
そして、もう1つ、「蒼穹のファフナー」で示されたことは、我々には「戻る」か「進む」かを選択する権利があるということです。けして、「戻る」ことが誤りであるとは言いません。「戻る」という選択もあるのです。しかし、それは唯一の選択ではありません。この文章で最も重要なポイントはここですね。素晴らしい未来の可能性を信じて、痛みのある世界に進むことも、自ら選び取ることができる選択肢の1つである、ということです。
そういう希望に満ちた語りも世の中にある、ということは非常に嬉しいことです。
結論 §
というわけで、これがパソコン通信対匿名掲示板システムに対する個人的な問題意識に対する1つの結論です。