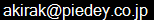本書の最後の方で意外にも興味深い文章に出会いました。
トンデモ本発生の原理についての考察です。
p386より
こうした「思弁する主体」の病理が、もっとも戯画化されて現れてくるのが、いわゆる「トンデモ本」の世界であろう。
(中略)
しかし、「トンデモ本」の著者達は、一様に生真面目である。彼らはたまたま独占的に知り得た原理なり知識なるを唯一の拠り所として、世界全体を説明し尽くし、かつ所有しようとする。それではなぜ、「説明」が「所有」にすりかわるのか。
「世界原理」は事象の外、メタのレヴェルにあるものだ。こうしたメタレヴェルから個別の事象を説明しつくすことによって、全事象は創造的に内面化される。すなわち「所有」である。
昔、けっこうトンデモ本は読みました。アダムスキーの本などは12冊(たぶん全部)読みました。エーリッヒ・フォン・デニケンの本を読んだこともあるし、トンデモ本の世界という本が出たときも楽しく読むことができました。縁が深いと言っても良いです。
しかし、トンデモ本は常に自然発生してくるのだろう、ぐらいの気持ちしか持っておらず、それが発生するメカニズムについて考察しうるというのは、実に新鮮な驚きとして感じられました。嬉しい驚きですね。
本書の説明を正しく理解したつもりはありませんが、こういうことを考察している人がいる、というだけで素晴らしいことだと思います。